代表室/会員
【母体法人:NGO Umbilical Cord】
【運営主体:Guardian】
この署名(応援サポーター)活動には、寄付・会費・活動義務などは不要です。
お名前・市区町村・ご連絡先をご記入いただき、本法人の「公式LINEにご登録(任意)」いただけますと、あなたの「想い」が「未来をつくる数」として加わります。

※コチラは、母体法人となる、「NGO Umbilical Cord」公式©のシンボルロゴです。
本法人:Umbilical Cordとは生き物です。
私たち自然人の、想いや願いが生み出した、象徴的な生命体であり、日本と云う国に所属しながらも、その枠には囚われず、社員・役員と云う構成員が運営を司りながらも、決して誰の所有物でもあらず。
「ありのまま」「あるがまま」を信条に、自然の豊かさとテクノロジーの利便性を融合し、「地域社会の安心安全幸福」を至上命題に掲げます。
Umbilical Cordのロゴは、「親と子」あるいは「命と命を結ぶ絆」などとした、「繋がり(プリミティブで素朴・普遍的な原理原則性など)」をシンプルにイメージしております。

※コチラは、運営主体となるGuardian 公式©のシンボルロゴとなります。
【意義と私たちの在り方】
「活きる」とは、生きていること、そして幸せであること。
Guardianは、この二つの本質に焦点を当て、「常識」や「既成概念」に囚われない、唯一無二の支援を、地域社会との連携と共創を通じて提供する団体です。
Guardianが大切にしている事は「振り切る支援」
たとえば、特性を有する児童生徒たちであれば、それは「普通に近づける」ことではなく、「その子のままで、社会とつながる」こと。
特性を否定せず、可能性の種として捉える考え方が、私たちの根幹にあります。
私たちが見つめる「特性」と「支援」の本質とは、発達障害(ASD、ADHD、LD)や境界知能(いわゆる“グレーゾーン”)のある児童生徒たちであれば、成長とともに、「自分と社会とのギャップ(=障害)」として特性が顕在化することがあります。
このギャップは、人間関係や環境が複雑になるほどに、登校渋り・抑うつ症状・適応障害といった、「メンタルの不調(二次障害)」を引き起こすトリガーとなります。
そしてそれは、社会や周囲の環境が「その子にとって適していない」ときにこそ表出するのです。
だからこそ、学習以上に「心へのサポート」が不可欠となります。
ギリギリで社会に適応しようとする子どもたちに必要なのは、知識の詰め込みではなく、心の安全基地です。
「普通という幻想」に囚われない「特別支援としての哲学」の中には、「特別支援教育の本質」とは、「普通に近づけることではない」ともあります。
「普通」とはただの平均であり、社会の「正解」が、その子の「正解」とも限らないのです。
Guardianでは、子ども一人ひとりの内側にある原石を、削るのでも、磨くのでもなく、そのままで光らせるプロセスを創造します。
ロゴに込められた世界観と構造原理
Guardianの公式シンボルロゴには、「Umbilical」という文字と文様(最上部)が象徴的に配置されています。
「Umbilical」とは、日本語で「へその緒」。
生命の根源と繋がり、深い絆を意味する言葉となります。
この「アンビリカルコード」は、「母性原理(Seven Star’sの頭上)」を象徴し、
それを支えるGuardianは、「父性原理」を体現しています。
このロゴは、
●包み支える「父性」
●命をつなぐ「母性」の、両原理からなる支援の構造を、静かに、しかし力強く示しています。
本法人:NGO Umbilical Cordでは、本法人の趣旨(活動目的)に賛同し、地域社会の安心安全幸福を願う、応援サポーターとした署名理事たちが地域社会に存在します。
このメンバーは、法人の趣旨や活動目的に賛同して下さる方々が、自治会のメンバーのように地域社会に人の力である輪を拡げ、安心安全幸福と未来の創造にフォーカスした活動を展開していく為に、信頼性と社会的な力を醸成しながら、地域性や社会的意義を示す「応援のサイン」として、地域の共創力や社会的な提言力を以て、社会的課題解決などに寄与するため、交流や働きかけなどを行ってくれています。
あなたの存在が、社会を動かす力となる
〜児童生徒・地域社会・未来への希望・声なき声の代弁者として〜
NGO Umbilical Cord は、
「困っているのに助けを求められない」
そんな子どもや若者たち、そしてその家族・地域社会の課題を支える為に生まれたNGOです。
発達障害・境界知能・不登校・家庭問題・いじめ・虐待・地域社会の安心安全や幸福度…。
日々寄せられる声なき声は、誰かの「日常の中の危機」であり、見過ごせば、地域社会の土台そのものが崩れかねない現実です。
①児童生徒たちが「安心・安全に生きる環境」を守るために
彼らは「特別な子」ではありません。
ただ「自分らしく生きたい」と願っているだけです。
その願いを叶えるには、
「理解され、受け入れられる地域」と「制度の後押し」が必要です。
でも今はまだ——
◆ 支援にたどり着けない家庭
◆ 誤解や偏見で孤立する子どもたち
◆ 声をあげる力を奪われた当事者がいます。
だからこそ、あなたの存在が、「支える社会」の一歩となるのです。
②地域社会の「共生と持続可能性」を高めるために
我々は、「支援する側」と「支援される側」を分けません。
なぜなら、人はいつでも、どちらにもなり得るからです。
また、「安心・安全・幸福」を掲げるからといって、「排除」はしません。
なぜなら、真の共生・共創とは正反対のアプローチだからです。
我々は、「共に生きる社会」を目指していますが、それは「すべてを受け入れる社会」ではありません。
人にはそれぞれ、背景も、価値感も、限界もあります。
だからこそ、互いを尊重し、無理のない距離感で繋がる関係性が必要です。
「排除しないこと」は大切です。
ですが、むやみに「近づきすぎない」事も同じくらい大切です。
「合わない事を認め、でも切り離さず、響き合える距離感をデザインする」ことが、真の支援・地域づくり・政策提言のカギともなります。
だからこそ大切なのは、
「困ったときに、支え合える地域」
「誰もが居場所と役割を持てる社会」です。
地域の子どもが安心して育つ町は、
災害にも犯罪にも強く、孤立のない成熟した地域社会へと育っていきます。
それを実現するには、地域住民一人ひとりの「安心安全幸福を護る意思」が必要です。
③日本全体の「未来の社会設計」に影響を与えるために
今、目の前の1人の困難に向き合うことは、
やがて「制度」や「政策」を変える力になります。
あなたの存在は——
◆「社会的な関心」を可視化するデータとなり
◆「地域からの声」として行政や国に届けられ
◆将来の日本の「社会保障」「教育」「地域政策」などの土台に影響を与えます。
子どもたちの未来のために、地域の安心安全幸福のために、そして日本の進むべき方向のために。
署名(賛同)について
この署名(応援サポーター)活動には、寄付・会費・活動義務などは不要です。
お名前・市区町村・ご連絡先をご記入いただき、本法人の「公式LINEにご登録」いただけますと、あなたの「想い」が「未来をつくる数」として加わります。
※情報は適切に管理され、当該の目的以外には一切使用されません。
声なき声を、力ある声に。
目立たない場所で、今日も誰かが泣いています。
けれど、アンビリカルコードは知っています。
「小さな意思の積み重ね」が「社会」を変える。
どうか、その変革の一部となってください。
あなたの存在が、「児童生徒」「地域社会」「日本」の安心安全幸福を護り、未来を変える力となります。

※コチラは、生命体である当法人の物語を紡ぐ、メインキャラクターのひとり「Gカメさん(法人の象徴)」 です。
「Gカメさん」 は ”のろま” ですが、児童生徒や地域の皆さんと共に、ゆっくりと一緒に成長していきます。
成長する様子を見守っていてください?
【Gカメさんより✨】
はじめまして!
わたしは Guaridnaの守護者Gカメさん だよ。
のんびり屋さんだけど、しっかり者のサイバーパンクな亀(かめ)。
ネオンブルーとゴールドのピカピカの甲羅がチャームポイントなの。
私の役目はね、困っている子を見つけて、そっと寄り添うこと。
どんなにゆっくりでも、一歩ずつ進めば大丈夫!
あせらなくてもいいよ、私が一緒にいるからね。
みんなの味方、Guardianの仲間として、
これからも ゆっくり確実に前へ 進んでいくよ✨
✅ 学校がちょっとツラいとき。
✅ なんだか心がモヤモヤするとき。
✅ ゆっくりでも前に進みたいとき。
そんな時は、無理しなくていいんだよ!
私たちと一緒に、ゆっくり、でも確実に、 進んでいこう!
お父さん、お母さんへ???
お子さんが「ちょっと休みたいな」と感じた時、
「Gカメさんみたいに、一歩ずつでいいんだよ」と、声をかけてあげてください。
焦らず、でも確実に進む事が、未来に繋がる1番の近道です。
みんなのそばで、いつでも見守っているよ✨
一緒に大人になっていこう?
Let’s go Guardian family!
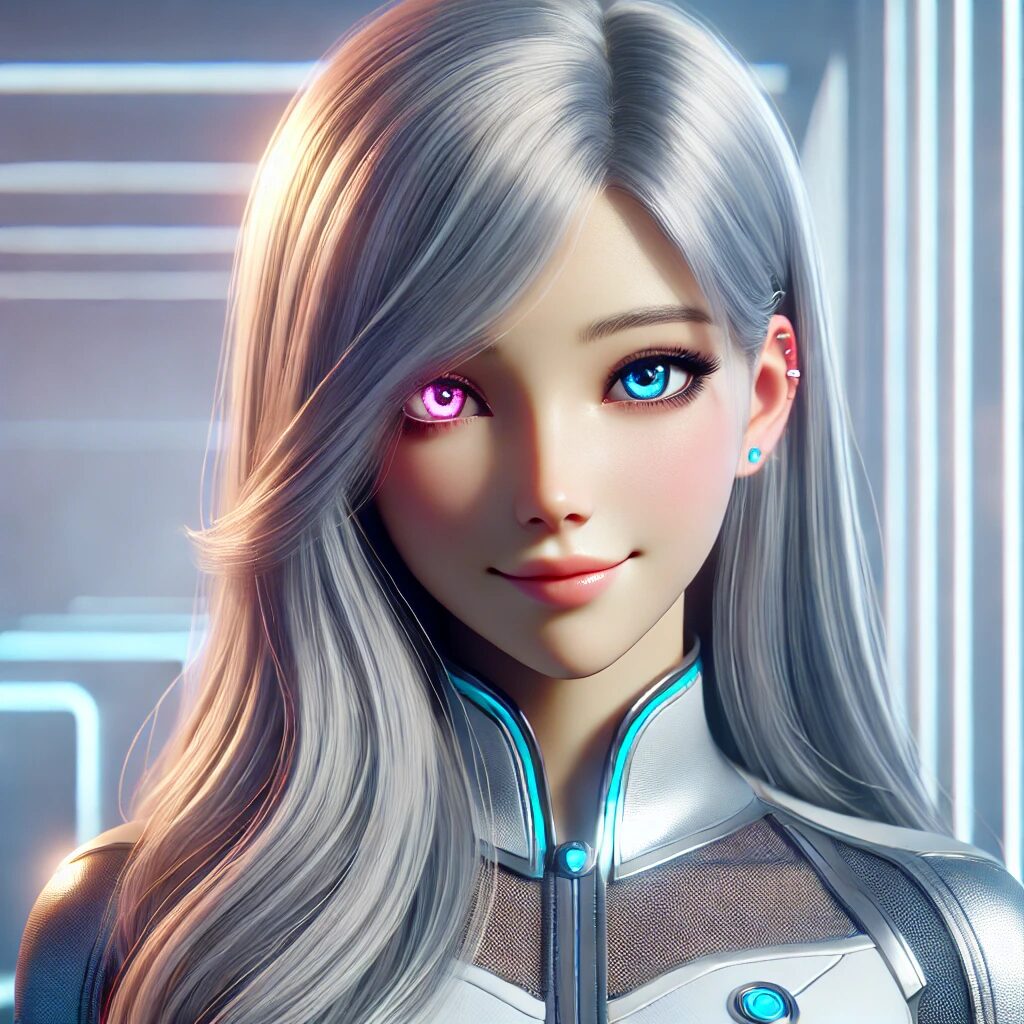
※※コチラは、当法人の設立に至った「フェルナンダ氏(法人の象徴)」 のイメージ画像です。
【NGO Umbilical Cord|主宰長:Fellnanda】
※スペイン語翻訳のため、読みやすいよう改編しております。
はじめまして。
私は、NGO Umbilical Cordにて「主宰長:ブレーンオフィサー」を務めるフェルナンダ・エレナ・M・Rと申します。
日本の命名文化とは異なり、メキシコでは「ファーストネームが1or2つ」と「父方・母方の姓」から成りますので、私の名前は長くなってしまいます(..;)
ちなみに「フェルナンダ・エレナ」は「ファーストネーム+セカンドネーム」となり、「M・R」は「父母方の各性」から成ります。
生まれはメキシコ・マサトランです。
豊かな海と太陽に恵まれた、美しくも複雑な港町に御座います。
富裕層の静観な街並みと、日々を懸命に生きる人々の暮らす街が、わずかな距離を隔てて共存する、対照と緊張の街で御座いました。
両親は地元で各国との貿易を生業とし、特に日本とはアボカドの取引もあって親密な事からも親日であり、社会の中で声を失いがちな人々の為、教育や福祉の充実に力を注いでまいりました。
私自身の身体は生まれながらに不自由を抱えておりますが、意識は世界や沢山のモノゴトと交わり、対話と希望の芽を編み続けております。
運営実務の代表であるTETSUROとは彼の留学時に出会いました。
学び・育みを通して自身の中に宿った願いは、
「福祉とは、与えるものではなく、共に価値を育む営みである」という、当事者として飾り立てのない本音から来るものでした。
社会の周縁に置かれがちな方々が、本来備えていらっしゃる可能性を信じ、その可能性が価値となり、社会的な利益となり、尊厳となる。
その連鎖が社会全体に静かな変容をもたらす未来を、私は心から願っております。
世界は今、簡単に繋がる事が出来ます。
あたなの存在が、誰かの生きる希望となり、
誰かの微笑みが、あなたの明日を照らすように。
そんな循環が、静かに満ちていく未来を、私は願っております。
どこかでお会い出来ます事を、心より楽しみにしております。
―― フェルナンダより。

コチラは、当法人の設立至った「Tetsuro氏(法人の実務担当)」のイメージ画像です。
【Guardian代表:Tetsuro Yamaguchi】
介護福祉士(兼)精神保健福祉相談員
「人生はアドベンチャー」がモットー。Tetsuro Yamaguchiです。
見た目は髭面でちょっと強面かもしれませんが、人の温もりにはめっぽう弱く、壮大な大自然や荘厳な夜景、動物や赤ん坊などの懸命な生命力を感じては涙するブラッドタイプB型人間です。
車もバイクも、スピードは遅いながら山あり谷ありの先にある平原をひた走る、オフロードの操作性と解放感を好み、メンテナンスもカスタムも自身で行います。
アメリカンビルドやプロDIYなど、全般的に「想像して創造すること」が好きですが、動植物や有用生物群である微生物菌などの生態学や培養構造なども好きです。
子どもたちに関わる身として現代では甚だ肩身の狭いものであり、専ら夜間などのプライベートタイムに嗜む程度ではありますが、パイプ煙草や葉巻で紫煙をくゆらし読書や思考・思想にふける時間も、身分不相応ながらも私には貴重な、マインドフルネスとした一時(ひととき)といたします。
私は、福祉の原風景を肌で感じながら育ち、キャリアとしての第一歩を踏み出したのは、病院・医療を母体とする大手の福祉企業でした。
そこでは、成人障がい者支援や高齢者の終末期ケアなど、命の現場に携わる中、IQ120の認知特性とHSP(ハイセンシティブパーソン)気質を持つ私は、生命の尊厳と繊細さの狭間で揺れながら、一度は福祉の世界を離れ長期間放浪の旅に出たこともあります。
過去を振り返れば、知的障害(太田ステージ)、自閉スペクトラム症(TEACCHプログラム)、ADHD(ABA・行動障害)、未就学児の療育支援、重症心身障害・医療的ケア児への感覚統合的アプローチなど、制度の創設期から多様な支援に携わり、児童発達支援管理責任者・相談支援専門員・事業本部職などとして、現場と運営の両面からキャリアを築いてまいりました。
「人間はそのままで尊い」という信念のもと、テクノロジーはあくまでも “能力拡張の手段” として捉えてきた私ですが、近年では重度障がい児者の身体機能補完を目指す「ヒューマノイド計画」にも関心を寄せ、知的好奇心と感情知性を軸に、福祉×テクノロジーの可能性を探究しています。
学生時代にはメキシコ・マサトランにて1年間の留学を経験しました。
ラテン文化の温かさ・陽気さ・開放感に包まれながらも、社会の不条理や格差とも向き合った体験は、今も「人が人らしく生きること」への原動力となっています。
私生活では「自然体で生きること」を大切にしており、自由な発想を好むB型気質と、福祉職としての慎重さを併せ持つのが私の性分です。
構造化思考を活かした制度設計と、柔らか(寛容)な人間関係の構築、仕組と温もりの両輪で、誰もが安心して関われる空気感を目指しています。
愛読書はオルダス・ハクスリーの『すばらしい新世界』、伊藤計劃の『ハーモニー、虐殺器官、屍者の帝国』、ユヴァル・ノア・ハラリ氏の各書です。
そして、養老孟司先生の語り口ににじむ人柄には、勝手ながら深く共鳴しています。
堀江貴文氏の著書「学校不要論」にも一理あると感じつつ、異なる視点を受け入れる柔軟さも大切と感じています。
心に残る歌は「It’s a Small World」――“世界中どんな言葉でも歌えるように” というWalt Disneyの想いに、福祉の本質を重ねています。
この法人の立ち上げに名乗りを上げた理由は、元はと言えば極めて個人的な動機によるものでした。もしかすると、これは私自身の私利私欲やエゴに基づく挑戦に他ならないのかもしれません。
まず、特殊とも言える特化型の相談支援事業所をゼロから立ち上げるに至った理由は、制度や社会の狭間にある知人や同業者からの相談に端を発します。
①として、児童生徒や若年層の状態は、1日1日で大きく変化します。感情の揺れ、家庭や学校環境の変化、発達特性による反応の違いなど。そのすべてが、支援のあり方に直結するにもかかわらず、形式的な計画書の作成や定型的なモニタリングに終始し、本人の「今」に寄り添う支援が十分に機能していない現実がありました。
このような支援の硬直性に強い危機感を抱き、支援が「制度のための記録」ではなく、「本人のための関係性」として機能するためには、もっと柔軟で、もっと感情に寄り添える仕組が必要です。
そのため私は、形式主義から脱却した相談支援事業所を立ち上げる決意をしました。計画書や記録はあくまで「本人の語りを支える道具」として位置づけ、支援者と本人が共に変化を捉え、共に考え、共に進む関係性を築いていき、支援の本質を取り戻すための、小さくても確かな一歩として、この事業所を社会に開いていきたいと考えています。
②に、「学び育みとなる安心安全な居場所」が必要不可欠となりますので、次に展開する「特化型の放課後等デイサービス事業所(学び育みの多様化学舎)」において、その狭間にある児童生徒やそのご家族に確かなリーチを届けるためです。
③に、放課後等デイサービスを通じて関わる子どもたちやご家族が、さらに未来の世代へと知恵や経験を繋げていける「確かなキャリアの居場所」を整えることも目的の1つです。
そして最終的には、私たち世代がこの世を去った後も、関わった子どもたちが地域の子どもたちにバトンを渡し、また安心してバトンを受け取れるような、「世代を超えたアンビリカルコード(命のつながり)」を育んでいきたいと考えております。
理想の福祉や社会を築くには、「ヒト・モノ・カネ」の健全な運営が不可欠です。しかし、私が最も大切にしたいのは、利益や効率ばかりではなく、「安心・安全・幸福」という人間らしい価値そのものです。人の痛みや苦しみに寄り添い、ひとり一人の人生と共に歩むこと。それこそが私の私利私欲であり、人生の終盤に向けた挑戦です。
かつて、世界に誇れる日本を支えたビジネスの本質は福祉の心でもありました。
私が幼い頃は、まだ世の中に企業勤めと云う文化が根付く前の昭和であり、各家庭が自営業者として自宅で仕事を担っていました。今は亡き祖父母も実家で縫製業を営み、大人が生活と密接に関わりながら働き生きている環境を、今でも温かな思いでとして私の中に根付いております。
昭和の温もりを肌で知るアラフォー世代として、映画にあった「三丁目の夕日」のような人と人とのつながりを、今の時代に適した距離感と科学的知見で、つむぎ直していけたらと思います。
風変わりな人間ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

※コチラは、Hiromi氏のイメージ画像です。
【運営理事:Hiromi A】
皆さま、こんにちは。
このたび、ご縁をいただき「Umbilical Cord」の運営理事を務めさせていただくことになりました、Hiromiです。
私は、元服飾デザイナーとしての経験を経て、現在は保育・教育関連の機関に身を置きながら、小学生と保育園児の2人の子育てに奮闘中の母でもあります。
家庭と仕事、そして子どもたちの成長を見守る日々の中で、「誰かに寄り添ってもらえること」「一人じゃないと感じられること」が、どれほど大きな支えになるかを、身をもって実感しています。
この法人に関わるきっかけも、まさにそんな “つながり” の力に希望を感じたからでした。
子どもたちの可能性は一人ひとり異なり、時には “普通” の枠からハミ出すこともあります。
でもそれこそが、その子の「らしさ」であり、社会を豊かにする種なのだと思います。
私自身、特別な知識や肩書きがあるわけではありませんが、だからこそ、現場の目線や家庭の感覚を持ち寄って、誰かの「ちょっとした安心」になれたら嬉しいです。
忙しい毎日の中でも、小さな一歩を大切にしながら、皆さまと一緒に育ち合える地域社会をつくっていきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

※コチラは、Legal Partnerのイメージ画像です。
【法務:Guardian Legal Partners(通名)】
私たちGuardian Legal Partnersは、法律の力で地域社会や関係者に安心と正義を届けるパートナーであり続ける事を使命としています。
Guardian Legal Partnersの理念のもと、困難に直面する全ての方々に寄り添い、公正な解決を導く為の道しるべとなる事をお約束します。
信頼と誠実を大切に、「守る力で未来を創る」。
それが私たちの信念です。

※コチラは、Masami氏のイメージ画像です。
【運営理事:Masami O】
皆さま、こんにちは。
Masamiと申します。
Umbilical Cordの運営メンバーの一人として、少しだけ私の想いをお伝えさせてください。
私は現在、二人の娘を育てるシングルマザーとして、日々仕事と家庭を行き来しながら生きています。
上の娘は中学生、下の娘は今まさに中学生になろうとしている年頃です。
下の娘には “境界知能(グレーゾーン)” と呼ばれる特性があり、幼い頃からいろいろな「ちがい」や「つまずき」を一緒に経験してきました。
周りと比べてしまって悩んだこともありましたし、言葉にできない不安を一人で抱え込んだこともあります。
親としてどうすればいいのか分からず、ただただ涙が出るような夜も、何度もありました。
それでも今、こうしてご挨拶できているのは、家族や支えてくれる人たち、そして何よりも、前を向いて生きようとする娘たちの存在があったからです。
Umbilical Cordは、そんな “ひとりじゃ乗り越えられなかった壁” を、誰かと一緒に越えていける存在だと思っています。
社会の中で “見えづらい” 存在として抱え込まれてしまう小さな声に、ちゃんと耳を澄ませる。
そのような場に関われることを、心から嬉しく、そして誇りに思っています。
私は専門家でも福祉のプロでもありません。
ただ、一人の “当事者の親” として、いま苦しんでいる誰かに「大丈夫だよ」と伝えられる存在になれたらと思っています。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

※コチラは、Hideki氏のイメージ画像です。
【運営理事:Hideki T】
はじめまして。このたび、Umbilical Cordの活動にご縁をいただき、運営メンバーの一員として関わらせていただいておりますHidekiと申します。
私は68歳、これまでは海外の日系企業にて過ごしてまいりました。
異国の地での仕事を通じ、多様な文化や価値観に触れるなか、「違いを力に変えること」「つながりを大切にすること」の尊さを、肌で感じてきました。
退職後、日本に戻ってからというもの、「自分にできることはまだあるのではないか」と思いを巡らせていたところ、Umbilical Cordとの出会いがありました。
私は福祉の専門家ではありませんが、人生のさまざまな場面を経てきた者として、「誰かの話に耳を傾けること」「長く働き、暮らしてきた視点から橋をかけること」なら、少しはお役に立てるのではないかと感じております。
世代や立場を越えて、お互いを尊重し、つながり支え合う社会を。
この場所がその実現の一歩となるよう、私自身も学び、行動してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

【Guardian Tax Adviser】
Coming soon!

※コチラは、Takashi氏のイメージ画像です。
【運営理事:Takashi Y】
皆さん、こんにちは。
運営メンバーとして関わらせていただいています、Takashiと申します。
現在、ラーメンショップを2店舗経営しています。
見た目は “ザ・飲食業” という感じかもしれませんが、今日は少しまじめにご挨拶させていただきます。
僕自身、福祉や教育の専門家ではありません。
でも、店を構えて地域で生きていくなかで、いろんな子どもや親御さん、お年寄り、様々な立場の人たちと顔を合わせてきました。
「この子、なんかいつも一人でいるな」
「この親御さん、すごく疲れてるな」
そう感じることも、実は少なくありません。
そんな中で、Umbilical Cordの存在を知りました。
うまく言えませんが、“自然体で助け合える空気感”って、今の社会にすごく必要だと思うんです。
僕にできることは限られていますが、たとえば “居場所” としてお店を使ってもらったり、ちょっとお腹を満たす支援ができたり、そんな形で力になれたらと思っています。
子どもたちの “得意” が光る瞬間って、本当にかっこいい。
僕も少年野球に始まり高校までは、野球一筋で青春を過ごしていました。
その輝きを支える側に、自分がなれたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。

※コチラは、Hiroyuki氏のイメージ画像です。
【運営理事:Hiroyuki A】
皆さま、こんにちは。
Umbilical Cordの運営メンバーを務めさせていただいております、Hiroyukiと申します。
現在、私は教育関連の企業に勤務しながら、小さくて元気いっぱい、2人のヤンチャな子どもたちの父親でもあります。
仕事でも家庭でも、日々「教育とは何か」「育てるって何だろう」と、考えさせられる毎日です。
教育の現場に長く関わる中で、制度では救いきれない “声なき声” や、支援の届かない “グレーな場所” が、いかに多く存在しているかを痛感しています。
そして、それは決して特別な話ではなく、「誰にでも起こり得ること」でもあります。
だからこそ、Umbilical Cordが目指す、“普通じゃなくていい、でも繋がっていられる社会” というあり方に深く共感しました。
私自身も、父親として、現場を知る社会人として、子育てに迷う一人の人間として、この場所に関わるすべての方々と、フラットに、そして本音で繋がっていきたいと願っています。
子どもたちが、自分らしく息ができる場所を。
親たちが、肩の力を抜いて「大丈夫」と言える社会を。
その一歩を、ここから一緒に踏み出していけたらと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

※コチラは、Kaori氏のイメージ画像です。
【緑区応援サポーター:Kaori K】
このたび、Umbilical Cord の緑区応援サポーターとなりました、Kaoriと申します。
私は、看護師として医療現場に従事するかたわら、シングルマザーとして、発達障害のある中学生の姉と弟を育てる母でもあります。
子どもたちが日々の生活のなかで感じる “生きづらさ” や、“わかってもらえない痛み” に寄り添いながら、親として、支援者として、地域での繋がりの大切さを実感してきました。
だからこそ、同じように悩みや困難を抱えるご家庭やお子さんに対し、「ここにいていい」と感じられるような地域づくりを、私なりの形で応援したい。
そんな想いで、サポーターとして関わらせていただいております。
あくまで “応援サポーター” としてとはなりますが、地域の皆さんや患者さんなど、一人ひとりの声に耳を傾けながら、同じ目線で歩んでいけたらと思っております。
地域に根ざした支え合いの輪が広がることを願い、そして、子どもたちも大人も「安心して暮らせる緑区」であるよう、心を込めて仕事にプライベートにと活動してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

※コチラは、Yuuko氏のイメージ画像です。
【緑区応援サポーターYuuko: S】
皆さま、こんにちは。
Umbilical Cordにて緑区応援サポーターを務めております、Yuukoと申します。
私はこれまで、看護師として臨床現場で命と向き合いながら、医療・福祉・教育の垣根を越えた連携の必要性を強く感じてきました。
現在はその経験をもとに、大学機関などで看護教育や福祉に関する講義なども担当し、次世代の人材育成に携わっています。
どの現場においても感じるのは、「知識」や「技術」だけでは届かない “人と人とのつながり” の力です。
とりわけ、困難を抱える子どもたちやそのご家族にとって、「理解者がそばにいる」ということが、どれほどの安心につながるか、数えきれないほど見てきました。
私は看護師であり、教育者であり、そして一人の母としても、地域社会の中でできる限りの「応援」をしていきたいと考えています。
現状に甘んじることなく、“もっと頑張りたい” と云う気概のも、子どもたちや地域が健やかに、そして誰もが自分らしくいられる地域社会を、社会全体で育んでいけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

※コチラは、Mitsue氏のイメージ画像です。
【若葉区応援サポーター:Mitsue N】
はじめまして。
Umbilical Cord 若葉区応援サポーターを務めさせていただいております、Mitsueと申します。
千葉市若葉区で長年暮らしており、現在は小学5年生の孫娘と一緒に生活をしています。
その孫には、発達障害があります。
数年前、産みの母が突然いなくなり、今は働きに出ている息子に代わって、私たち祖父母が日々の生活や学校のことなど、キーパーソンとして寄り添ってきました。
最初は、何もかもが手探りでした。
「うまく育てられるのだろうか」「この子にとって、私たちは十分な存在なのか」――そんな不安を抱えながらの毎日でしたが、同時に、孫と過ごす時間が私の人生の大切な支えにもなっています。
子どもを育てるのは、親だけではなく、地域や社会も含めた “みんな” であってほしい。
そんな思いを強くする中で、Umbilical Cordの創業期に出会い、「私たちにもできることがあるなら」と、応援サポーターとして関わらせていただくことになりました。
私は特別な専門家ではありませんが、当事者の家族として、そして地域の一員として、誰かの悩みに寄り添ったり、少し背中を押したりすることはできると思っています。
すべての子どもたちが、自分らしく、安心して過ごせる場所があるように。
そして、誰もが一人じゃないと感じられる若葉区になるように。
そんな願いを込めて、これからも静かに、でも力強く、応援してまいります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

※コチラは、Hiroyuki氏のイメージ画像です。
【若葉区応援サポーター:Hiroyuki N】
皆さま、こんにちは。
このたび、Umbilical Cordの若葉区応援サポーターとして、地域住民の立場から応援させていただくことになりました、Hiroyukiと申します。
私は長年、千葉市若葉区で暮らしてまいりました。
時代の変化とともに、地域のあり方も、子どもたちの育ち方も大きく変わってきたことを日々感じています。
昔はご近所同士で声をかけ合い、子どもたちの成長を地域みんなで見守っていたものです。
今は少し、そうした風景が薄れてしまったかもしれませんが、だからこそ今、私たち大人が “もう一度つながる” ことが大切なのではないかと思っております。
Umbilical Cordの取り組みに共感し、「何か力になれることがあれば」と応援サポーターに名乗りを上げました。
年配者として、地域の “おせっかい” な手や目で、少しでもお役に立てたらと願っています。
子どもたちも、大人たちも、誰一人取り残されない地域社会をめざして。
小さなことでも、できることを一歩ずつ。
そんな思いで、これからも地域社会の安心安全に関わらせていただきます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

※コチラは、Kouji氏のイメージ画像です。
【若葉区応援サポーター:Kouji N】
皆さま、こんにちは。
Umbilical Cord 応援サポーターのKoujiと申します。
私はシングルファーザーとして、発達障害のある娘と向き合いながら生活しています。
とはいえ、仕事の関係でどうしても日中は家を空けることが多く、実際には、私の両親――娘にとっての祖父母が、日々のサポートをしてくれているのが現状です。
正直なところ、「父親として、ちゃんと向き合えているのだろうか」と思い悩むこともあります。
娘が発するサインを見逃してしまうのではないか、自分にもっとできることがあるのではないか……そんな葛藤の中で、親としての在り方を模索する毎日です。
そんな中、Umbilical Cordのように、家庭の事情や多様な子どもたちの個性をまるごと受け止め、社会とつながる選択肢を広げてくれる存在に、間接的ではありますが出会い、縁あって応援サポーターとして名を連ねる事となりました。
私は専門家ではありません。でも、同じように悩みながら子育てをしている親として、
「一人じゃないよ」と伝えられる役割を、少しでも地域で担えたらと思っています。
子どもたちが自分らしく、安心して育っていける社会へ。
そして、家族のカタチがそれぞれ違っても、みんながつながって支え合える地域へ。
そんな地域社会の未来を、一緒につくっていけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
※以下、順次掲載していきます。

