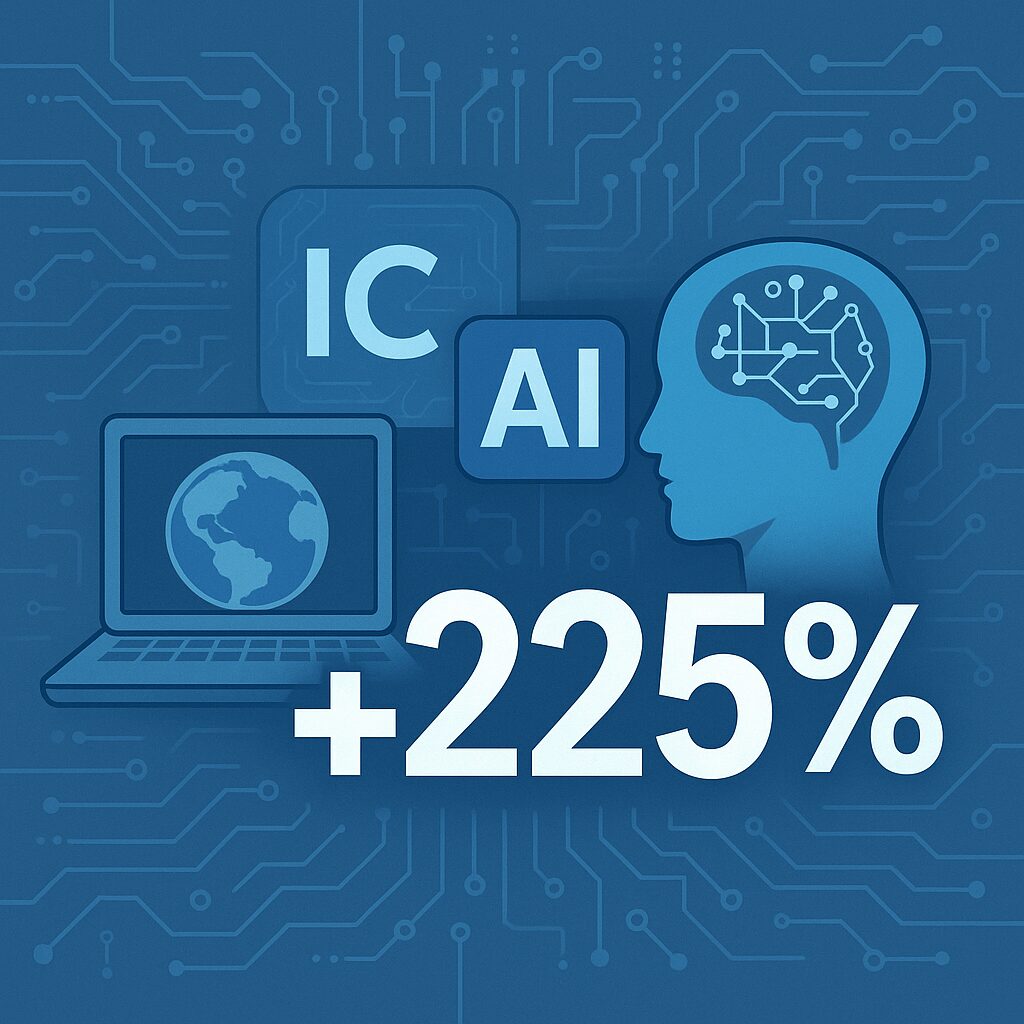
🧠AI・ICT・IOTを駆使したDX戦略
スローガン
– 能力拡張225% –
まずはじめに、「DX戦略」とは
DX(デジタル トランス フォーメーション)とは、AIやICTなど「デジタルの力で、生活や仕事・身体機能のあり方を “もっと便利に・もっと自由に” 繋げていくこと」を言います。
もっと「かんたん」に言うと…
■今まで当たり前で限界だったことを、「デジタル」を使ってラクにしたり、付加価値を実装したりすること。
■たとえば・・・、
・紙に書いていた宿題を → タブレットでやる
・電話で連絡していたことを → LINEでパッと伝える
・教室に行けなかったら → オンラインで参加する
・歩行に困難があったら→ オートメーション機能で歩行補助する
それらが、DX(デジタル トランス フォーメーション)です。
どうして大事なの?
■今の社会は、パソコン・スマホ・AI・ICTなしでは動かないくらい、デジタルが中心です。
■DXをすすめると、
・苦手なことを補える
・好き・トクイなことを伸ばせる
・家にいても社会とつながれる
・将来の新たな生き方や働き方にもつながる
児童生徒・家族・地域にとって
| ダレにとって? | DXがあると… |
|---|---|
| 児童生徒 (子どもたち) | 「できない」から、「できるかも」「できた」へ変われる |
| 保護者 (おかあさん・おとうさん) | 「この子の未来が見えない…」から、「この子にしかできない未来がある」へ |
| 地域社会 (みんな) | 多様な子どもたちが、活躍できる社会をつくれる |
DXって、「ムリ」を「できる」に変える魔法みたいな力
パソコンやAI・ICTは、「自分らしさ」を光らせる現代の「魔法(まほう)」
基本理念
Umbilical Cord、Guardianでは、PC・ICT・AI・テクノロジーの力を積極的に活用し、「普通」ではなく、「異能」を社会的価値へと変換するための、「DX型支援モデル」を推進していきます。
本法人では、PCスキルやICTリテラシー、AI活用力といった、自分を護り抜き時代を生きるための盾の武器を、従来の支援領域に組み込む事でトランスヒューマニズムとし、児童生徒の潜在能力を・・・、
⚡+225%拡張
することを目標としています。
研究出典と根拠(一部)
| 出典 | 内容 | 拡張領域 |
|---|---|---|
| OECD(PISA, 2020) | EdTech活用による学力向上 | 認知能力 +15〜25% |
| Stanford大(2019) | AI学習支援による個別最適学習 | 認知 +40% |
| MIT Media Lab(Scratch研究) | 表現力が2〜5倍になる傾向 | 表現力 +300%前後 |
| Adobe Creative Education調査(2019) | ICT活用学生は創造的自信が+280% | 創造性 |
| NSF(米国科学財団) | STEM教育による非認知能力強化 | 自己効力感 +50%以上 |
ビジョンに基づく3つの主眼
①【児童生徒にとって】
■潜在能力を「光」として解放
■表現が困難な子も、デジタル空間で「居場所」と「役割」を得る
■異才を「社会貢献型スキル」に変換する支援
②【ご家族にとって】
■「この子は働けるのだろうか」から、「この子にしかできない働き方がある」への認知変革
■ご家族も一緒に、ICTリテラシーを学ぶ「共育型DX」
■将来設計が描けることで、家庭の安心感と希望を支援
③【地域社会にとって】
■テクノロジーを活用した支援で、「地域の異才」が地域の力に
■働く・関わる機会が乏しかった層が、メディア・地域事業・イベントで活躍
■地域社会に、新しい多様性の価値軸をもたらす
DX的支援プロセス(4ステージモデル)
| ステージ | 内容 | 支援内容(例) | ゴール |
|---|---|---|---|
| ① 能力拡張 | デジタルで「できる」を増やす | 基礎学習 PC・ICT GPTs Scratch Canvaなどの習熟 | 潜在能力+225% の開花 |
| ② 可視化 | 成果・作品を見える形に | ポートフォリオ作成、SNS発信、イベント展示 | 表現力+500% 自信・評価の獲得 |
| ③ 社会接続 | 社会とのつながりを構築 | オンラインサロン、メタバース、外部ワーク体験 | 所属感 と 役割 の獲得 |
| ④ 出口 ↓ 出口戦略 | 社会での自立的役割へ | 実践、クラウドワーク、自営活動、支援者化 | 自立 価値 貢献 のサイクルへ |
出口戦略:5タイプのロールモデル(例)
| タイプ | 説明 | (例) |
|---|---|---|
| テク職型 | 動画・画像・WebなどのICT職能役割 | デザイナー/編集者/ライター |
| クリエイター型 | ゲーム実況・イラスト・音楽制作 | VTuber/音楽投稿者 |
| 支援者型 | 自身の体験を活かすメンターやスタッフ | ピアスタッフ/家庭支援者 |
| 探究型 | 興味に特化した調査・知識型活動 | リサーチャー/コンテンツ制作 |
| 感性型 | 感覚・世界観の表現に特化 | 写真・詩・空間演出作家 |
実践的学習のエビデンス(能力拡張性)
「+225%」の算出構造(構成要素)
これは、以下4つの能力要素をもとに、拡張率の中央値を統合して得た概算値です。
| 効果指標 | 出典・研究 | 拡張率(例) |
|---|---|---|
| 認知能力 | スタンフォード大学 OECD | +15%〜+40% |
| 非認知能力 | ルンド大学 アメリカ国立科学財団 | +30%〜+60% |
| 表現力 | マサチューセッツ工科大学 Apple | +100%〜+500% |
| 創造力 | ハーバード大学 Adobe | +50%〜+300% |
統合による試算(中央値モデル)
| 項目 | 最小〜最大拡張率 | 中央値 | 重み係数(仮) |
|---|---|---|---|
| 認知能力 | +15〜+40% | +25% | ×1 |
| 非認知能力 | +30〜+60% | +45% | ×1 |
| 表現力 | +100〜+500% | +300% | ×0.5(感性領域の個人差を考慮) |
| 創造性 | +50〜+300% | +175% | ×0.5(分野差を考慮) |
➡ 総合して、児童生徒の「潜在能力」は「⚡+75%〜+225%」の拡張が可能と推定。
実装プラン:DX支援モデル(例)
| 要素 | 内容(例) |
|---|---|
| プログラム名称 | Guardian’s Lab, |
| 使用ツール | GPTs, Canva, Scratch, OBS, Discord, Notion |
| 支援構成 | 初級:ICT × 遊び 中級:ICT × 表現 上級:ICT × 社会貢献 |
| 成果可視化 | 作品展示会 オンライン発表 実務連携マッチング |
| 地域社会の巻き込み | 「地域ICT学習会」 「未来設計カンファレンス」の開催 |
地域社会との連携戦略(例)
■地元中小企業・団体・個人事業主・個人クリエイターとのDX共創プロジェクト
■商工会・自治体と連携した「デジタルで繋がるまちづくり」
■地元の企業や学校に「デジタルアンバサダー」として児童生徒が交流参加
独自価値
「普通を目指さず、“特性・個性・異端・異能” をテクノロジーから尖らせる」
特性・個性・異端・異能 × テクノロジー
= 新たなインパクト&シナジーと社会的役割の創出(地域共創社会の実現)
■DXの推進は、児童生徒の 生き方・働き方の自由度 を広げ・・・、
■ご家族に 「我が子にも発展的な未来がある」 という確信を与え・・・、
■地域社会に 多様性と共生共創のモデルケース を提示します。
被支援者が革命者となる静かな変容
法人内部DXは「外(そと)」に波及する
〜 静かなる革命は、内から始まる 〜
基本視点
本法人が内部で進めるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なる業務効率化ではありません。
それは、支援の質を高め、スタッフと組織をアップデートし、最終的には「支援されていた存在=児童生徒など」が、社会の変革者・創造者として舞台に上がる可能性を広げる静かな革命です。
3つの「変容」の連鎖
| 変容の レイヤー | DXによる 変化 | 社会への影響 |
|---|---|---|
| ①組織の 変容 | ICT/AIを活用した記録・連携・教育の最適化 | 支援の質と数の最大化 |
| ②STAFFの 変容 | 業務の知的進化、時間と余白の再分配 | 「支援者の支援者」へ進化、地域人材力向上 |
| ③ 児童生徒の変容 | 支援を受けていた立場から、自ら表現・貢献する存在へ | 「支援される側」が「社会の希望」へと流転 |
被支援者が静かな「革命者」となる未来
PC・ICT・AI・テクノロジーは、
■話せない子に「伝え合う手段」を、
■不器用な子に「表現する道具」を、
■人と関われなかった子に「繋がる世界」をもたらします。
そして、その道具を手にした子どもたちは、自らの人生を変えるだけでなく、「同じような誰かの未来」までも照らしうる存在となるのです。
それは、
誰にも気づかれなかった「小さな声」が、世界を変容する「静かな革命」。
内部DX×社会貢献モデル
| 項目 | 変化・インパクト |
|---|---|
| ✅ 業務のDX | 記録・共有・評価・計画の効率化 → より多くの支援へ |
| ✅ スタッフのDX | ICT教育/AI研修 → 地域に還元できる人材化 |
| ✅ 児童生徒のDX | 自己表現・創造・社会接続 → 作品・スキルが「役割」に |
| ✅ 波及効果 | 他団体・保護者・学校へのノウハウ提供 → 地域全体の福祉力向上 |
| ✅ 革命的転換点 | 「支援を受けるだけ」から「誰かを支える存在」へ |
「静かなる革命は、ここから始まる。」
「支援のDXは、希望のインフラとなる」
「支援される子が、誰かの光となる未来へ」
「支援の質と組織の知能化を通じた、地域共生型DXと希望循環モデルの実装へ」
本法人の内部DXは…
■「業務改善」ではなく、「未来設計」
■「支援の最適化」ではなく、「存在価値の再定義」
■そして、「被支援者」が「支援者」となる静かな変容を、内側から地域社会へ拡げるもの

