
【趣旨】
「こども110番」の盾
当参加型支援は、発達障害・境界知能・精神疾患など、認知・精神的な特性によって複合的困難を抱えてきた若年層を対象に、その人らしい役割や誇りを支援し、Guardian Familyの一員として地域社会の安心安全を共に築いていく事を目的とした、少し特殊で社会的意義の高い人材育成にフォーカスした児童生徒参加型支援となります。
Guardianでは、「共に歩む仲間(関係する全ての人々)を選び合う事は大切」と考えています。
【対象】
①児童精神科を入退院の児童生徒(発達障害等)
②児童養護施設で生活の児童生徒(発達障害等)
③児童保護施設を退院の児童生徒(発達障害等)
【登録条件】
■受給者証、持っている方は「精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・身体障害者手帳」のいずれか
■保護者との事前面談
・行動歴などのヒアリング
・本人や保護者の支援受容や役割確認
■心理検査資料の提出
・WISC、医療機関等の意見書など(過去1年以内)
■Guardian独自の特性検査(テスト受講)
■入退院・施設歴に関する情報資料
・医療・児童福祉・保護機関等からの紹介状
・生活歴や支援歴の時系列要点
■その他
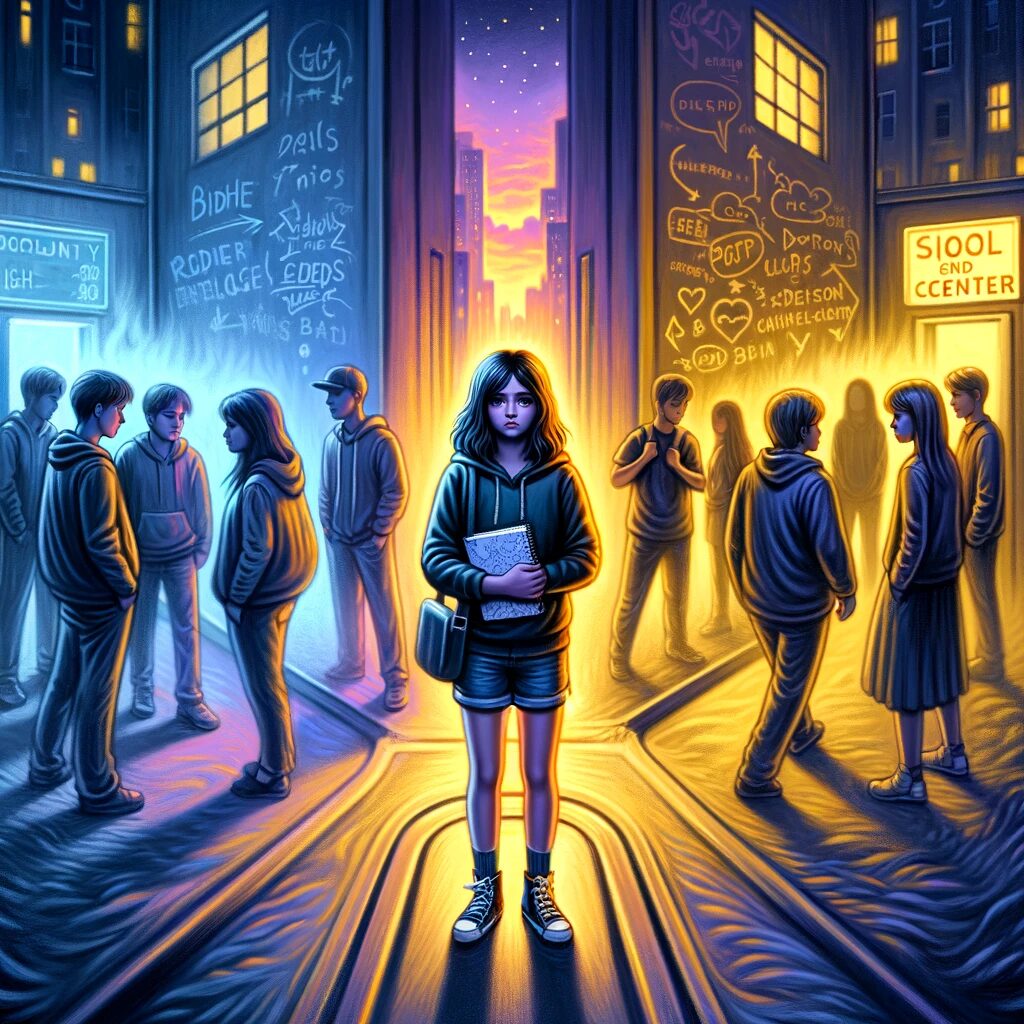
【支援領域表】
一見、「社会不適応」や「問題」と見なされる事のある人々であっても、その背景には診断未確定の発達障害、境界知能、精神的トラウマや不適切な環境による情緒不安定など、支援の不在によって生まれた「認知的・精神的被害」が隠れているケースは少なくありません。
①児童精神科入退院児の例
| タイプ | 主な特徴 | 背景事情 | 支援上のポイント |
|---|---|---|---|
| 情緒不安定型 | 不安・抑うつ・情緒起伏が激しい/OD・自傷 | 愛着障害・家庭内不和・いじめ被害 | 安心安全な空間提供と感情ラベリング支援 |
| 発達障害×精神疾患併存型 | ASDやADHDと共に不安障害・双極性など | 二次障害としての精神症状/誤診・未診断 | 特性に応じた構造化×精神安定支援 |
| 解離・トラウマ型 | 記憶飛び・空間把握困難/離人感 | 虐待・性被害・ネグレクト | 安定化優先・トラウマインフォームドケアが前提 |
| 依存傾向型 | 過剰な他者依存/OD・SNS依存など | 孤立・愛着不全・養育者の不在 | 共依存を防ぎつつ、安全基地として支援 |
| 拒絶・引きこもり型 | 会話拒否・行動拒否・閉じこもり | 被虐待・学校不適応・抑圧的家庭 | 接触よりも「見守りの場」から関係性構築 |
②児童養護施設生活児の例
| タイプ | 主な特徴 | 背景事情 | 支援上のポイント |
|---|---|---|---|
| 無力感・自己否定型 | 自信がなく「何もできない」発言が多い | 養育放棄・虐待/強い比較体験 | 成功体験の蓄積と「意味づけ」の支援 |
| 対人不信・疑念型 | 他人に心を開かない/関係断絶 | 施設間移動・裏切り体験 | 時間をかけた関係構築と肯定的対話 |
| 過適応・いい子型 | 支援者には従順/実はストレス過剰 | 評価への依存/施設内役割期待 | 「評価されない場」でも安心できる体験設計 |
| 自立志向過剰型 | すぐに一人暮らし・就職を志向/相談拒否 | 過去の管理体験への反発・自由願望 | 段階的な自立設計と「一人でやらなくていい」支援 |
| 家庭幻想固執型 | 親への固執/面会・連絡への執着 | 家庭での未解決な想い・保護体験 | 感情整理と「過去の物語」の再定義が必要 |
③児童保護施設退院児の例
| タイプ | 主な特徴 | 背景事情 | 支援上のポイント |
|---|---|---|---|
| 反抗・破壊型 | 怒りの爆発、暴言・暴力 | 虐待、施設転々、親の精神疾患 | 感情の言語化支援と衝動制御の再学習 |
| 巻き込まれ型 | 仲間に流され非行、加害行為 | 他者に逆らえない性格・家庭抑圧 | 自己決定力と「断る練習」が必須 |
| 性搾取・SNS依存型 | 援交・露出・配信等/承認欲求 | 愛情不足、過去の被害体験 | 自己価値の再構築支援、急がず信頼構築 |
| 認知特性型(ASD・境界知能) | 状況理解のズレ、冗談→問題行動 | 誤学習、社会的視点の弱さ | 構造化支援とルールの視覚化が鍵 |
| 家庭崩壊・生活困窮型 | 窃盗・詐欺・逃避行動 | 貧困・ネグレクト・依存症家庭 | まずは「衣食住の安定と安心」が最優先 |
| 誇大・支配型 | 「俺はすごい」「悪事を自慢」 | 劣等感の裏返し・承認不足 | 表面の強さの裏の空虚を理解し、役割支援へ |
児童福祉領域支援の可否
自傷や依存、感情調整の困難があっても、「自分を変えたい」という小さな意志を尊重し、精神的・認知的背景を踏まえた学習支援を行います。
| ?項目 | ✅支援「可」 | ❌支援「不可」 |
|---|---|---|
| 主体性 | 「出発したい」「社会と繋がりたい」という意思がある | 支援を操作・利用しようとし、自ら変わろうとする意志がない |
| 関係性 | 支援者との信頼関係を築こうとする姿勢がある | 対話拒否や他者依存が強く、支援の妨げになる関係性を持ち込む |
| 誠実性 | 誤魔化しがあっても、正直になろうとする意思がある | 虚偽・隠蔽・二重生活を継続し、改善意欲が見られない |
| 精神・認知的安定性 | 精神的に不安定でも、自己理解や改善意欲がある | 他者に危害を加える可能性が高い、または共依存関係に陥る恐れがある |
| 変化への姿勢 | 小さな事でも「変わりたい」というきっかけを大事にできる | 支援を受けながらも、周囲や制度への敵意・攻撃性が著しく強い |
※児童福祉領域での支援となりますので、支援可能可否は、Guardian内部の評価基準に基づき、協議または倫理会議を経て決定されます。安全性・信頼性・関係性意欲を総合的に勘案します。

共通して多い背景
各タイプの背後には、「発達特性」「認知理解のズレ」「精神疾患未診断」「二次障害」などが重なっているケースも多く、発達障害・境界知能・精神疾患など、精神的・認知的背景が見過ごされたまま、困難へ繋がっている可能性もある。
Vision Statement
「護られる側」から「護る側」へ
― 発達・精神的特性を抱えた若者の出発が、地域社会のレジリエンスを高める力となる ―

1.問題提起:社会的排除(居場所の喪失)が再び「負の循環」へ
今日、家庭や学校、地域社会の狭間からこぼれ落ちた児童生徒たちは、「不安定な存在」として、腫れ物にでも触れるように見過ごされてきた歴史があります。
しかし、その多くは「守られるべきだったのに守られなかった人たち」= 社会的被害者でもあります。
2.ビジョン:社会的出発が、地域社会の護り手をも生み出す
Guardianは信じます。
過去に苦しみや逸脱があったとしても、「もう一度、始めたい」と願う心を持つ限り、人は何度でも社会と繋がり、地域社会や他者を護る存在になれるという事を。
Guardianの思想は、「可哀想な人(社会的弱者)を助ける福祉」ではありません。
社会の本質的なレジリエンスを育む「地域戦略」であり、「人材育成」です。
3.Guardianが描く4つの段階的ビジョン(Guardian Family化)
| フェーズ | 支援段階 | 主な内容 |
|---|---|---|
| Phase 1 | 心理・発達特性の理解から始める関わり | 相談支援→安定化支援→専門機関連携 |
| Phase 2 | 共にある存在としての関わり | 自助活動・ピア支援者としての関与、役割意識の醸成 |
| Phase 3 | 地域と繋ぐ存在としての関わり | イベント運営補助、後輩支援、学校や地域との協働 |
| Phase 4 | 守る側=支援者・地域社会の盾としての関わり | サポーター、スタッフ、ボランティア、当事者講師などへの移行 |
「あの子が、いま、地域の見守り隊(こども110番の盾)として活動している」
「過去に問題を起こした彼女が、今では児童生徒らの安心安全に寄り添っている」
そんな「社会的信頼」の物語を、Guardianは地域社会に醸成していきたいのです。
4.地域社会への呼びかけ:あなたも「護り(盾)の仲間」に
入院歴のある人、施設出身の人、依存症から回復しようとしている人など・・・。
そんな彼女・彼らが、Guardianたるガーディアンとなり、ピアサポーターとなり、未来を担う児童生徒たちを支える側へ立つ姿を、世界の歴史は数多く見てきました。
これからは、「護られる側」と「支援する側」の境界をなくし、誰もが「地域社会の護り手」になる、そんな社会を築いていく時代です。

「みんなで街を守る。未だ見ぬガーディアンが、ここから誕生する」
「ピンチだった人は、今度は誰かを助けるヒーローに変わる」
「護られてきた人々が、護る側に立つ。」
「護る側に立ちたい」 ーー そんな若者たちを、Guardianは希望を託し支えます。
進路設計ガイドライン
基本理念
生きづらさを抱えた児童生徒に対して、「社会的な居場所」と「自分らしい生き方」を見出す為の、実践的な進路設計指針の例。
女子編:『自分らしく生きる人生設計』モデル
進路モデルの構造
| ステップ | 内容 | 支援ポイント |
| ① 自己理解 | 好き・得意・嫌いを言語化 | IDMモデルによる支援(Identity) |
| ② 仮体験 | 興味のある分野で短期的な体験 | 環境安全性、女性限定空間の確保 |
| ③ 小さな挑戦 | リモートワーク、SNS発信など | 成功体験の言語化と可視化支援 |
| ④ 自立への道 | 副業・就労・個人事業主など選択肢提示 | 継続的支援、外部メンターとの連携 |
想定進路・分野(例):
保育補助/ネイル・美容系/動画編集・デザイン/ハンドメイド/福祉系事務 など
外部連携先:
女性起業支援団体・福祉的就労支援・地域女性センター・民間サロン など
その他:
資格取得、自分の物語・表現作品の制作、共感発信者への転生、メンター体験、作品販売体験など
男子編:『弟子入りから一人親方へ』モデル
進路モデルの構造
| 段階 | 内容 | 支援ポイント |
|---|---|---|
| ① 見習い体験 | 数日間の職業体験(建築・整備・農業等) | メンターとの相性確認、安全配慮 |
| ② 弟子入り | 一人親方の元で正式に見習いを始める | 寮・住居の確保、生活支援・金銭管理 |
| ③ 半自立 | 技術習得+現場実務者化 | 資格取得支援(例:電工・建築士補) |
| ④ 独立 | 自分の屋号で請負や事業開始 | 創業支援、資金調達、後方支援体制 |
想定業種(例):
建築大工/電気工事/内装・塗装/配管・整備/農業・漁業/木工 など
外部連携先:
商工会・建設業協会・ハローワーク・地域の職業訓練校 など
その他:
資格取得、現場記録のドキュメント化、道具へのこだわり発言、弟子・後輩育成、コンテスト参加など
地域貢献活動参加
1.過去よりも「これから」を起点に。
2.社会の中に「自分の居場所」を。
3.専門職や地域との信頼関係の架け橋を。
4.小さな成功体験を積み自信と希望を。
| 生活支援系 | 高齢者宅のお手伝い、ゴミ拾い・清掃活動、商店街チャレンジ、フードドライブなど | 社会に貢献し、誰かの役に立っている実感 |
| 子どもサポート系 | 絵本の読み聞かせ活動、小学生への学習支援、遊びリーダー活動、ベビーシッター体験など | 誰かを笑顔にする、自分に気づける体験 |
| 動物・自然支援系 | 地域猫の見守りボランティア、公園の花壇整備・植物の手入れ活動、保護犬施設や動物園での軽作業手伝い、地域の農園ボランティアなど | 命や自然を、大切にする優しさを育む体験 |
| 文化・発信系 | イラストや手作りグッズの寄贈、地域の情報誌や掲示板への投稿、SNS発信ボランティア、ハンドメイド作品でバザーやチャリティ参加など | 自分の「好き」や「得意」が、誰かの為になる喜び |
| イベント協力・受付系 | 地域祭り・バザーの受付や案内係、子ども向けブースの運営補助、縁日の手作り出店、マルシェやイベントの装飾作りなど | 地域の一員として、「場を創る」喜び |
| 心の支援・繋がり系 | 孤立している人へのお便りプロジェクト、施設への応援メッセージ・イラストカード作成、心のお守り作り、地域の見守り活動に一緒に参加など | 心を届けて、誰かの安心を生む優しさ |
| 防災・安全見守り系 | 防災マップ作り、非常持ち出し袋の点検&ポスター作り、防災クイズ大会や防災紙芝居の出張実演、登下校の安全見守りサポートなど | みんなを護る、力になれる誇らしさ |
| 多文化・地域交流系 | 外国にルーツの子どもと遊び「ことば交換遊び」、海外の文化を紹介する掲示物作り、留学生や地域の外国人との「ことばカフェ」開催補助、ようこそカード作作成(日本に来た子どもへのウェルカムメッセージ)など | 違いを認め合い、繋がる喜び |
| 心の護り服プロジェクト、ファブリックアートなどの...「衣」系 | 地元の作業所や洋裁工房などと連携して、「安心感」や「感覚過敏」配慮の服を企画、廃材を使ったアート作品や小物を共同制作など | 地域の技と子どもの感性がつながり、福祉・教育・経済が循環する共創モデルの実現 |
| 地元農家との「こども農園」&ブランド化、加工品の開発「心のおやつ」などの...「食」系 | 発達特性のある児童生徒らも参加出来る農業体験、地元の製菓業者と共同で「気持ちが落ち着く味、集中しやすい栄養素」などを含んだオヤツ開発など | 子どもの特性に寄り添った“育む食”を通じて、地域の産業と感情価値がつながる共生の場づくり |
| 子ども専用「ココイルハウス」モデル開発、廃材×DIY×ワークショップなどの...「住」系 | 地元工務店・建築士などとの共同で、発達特性児の「落ち着く空間」プロトタイプを開発、建材業者や家具職人などと君で、廃材や余剰材を使った「一緒に創る自分だけの空間」など | 子どもの安心と創造性をカタチにする、“共に創る居場所デザイン”による地域循環型ものづくり |
| 地元企業と「センサリーグッズ」の開発、アロマ・自然素材商品との連携などの...「医」系 | トランスヒューマン系の触覚強化グッズを地元メーカーと開発、精神安定に寄与する自然由来の香りや素材を使った製品開発など | 感覚とこころを整えるテクノロジーと自然の融合で、未来型ウェルビーイングを地域から創出 |
他・・・
■地域・施設連携型:有償ボランティア → 小規模請負
■クラウドワークス連携・在宅副業導入
■チーム単位の「職業訓練受託」
■サブスク型防犯
■企業や商店街との「防犯パトロール契約」
■防犯教育・啓発活動の出張プログラム
■地域防犯アプリ×パトロール連携
■防犯カメラ設置代行・点検&相談事業など・・・。
可能性は無限大✨

