
テクノロジーが発展した現代においても、読書をすすめる理由。
1.深い思考力を養える – SNSや短い記事では得られない、論理的思考や深い洞察を育む。
2.情報の質が高い – インターネット上の情報は断片的だが、本は専門家による体系的な知識が得られる。
3.集中力を鍛えられる – デジタル時代のマルチタスクで失われがちな「没入する力」を取り戻せる。
4.デジタル疲れを軽減する – 画面を見続けるストレスから解放され、リラックス効果を得られる。
5.想像力と創造力を高める – 文字だけの世界を脳内で構築することで、クリエイティブな発想が養われる。
※デジタル百科事典はコチラ(Britannica Japan)
テクノロジーの進化により情報が溢れる時代だからこそ、読書を通じて「深く考える力」を維持することも重要です。
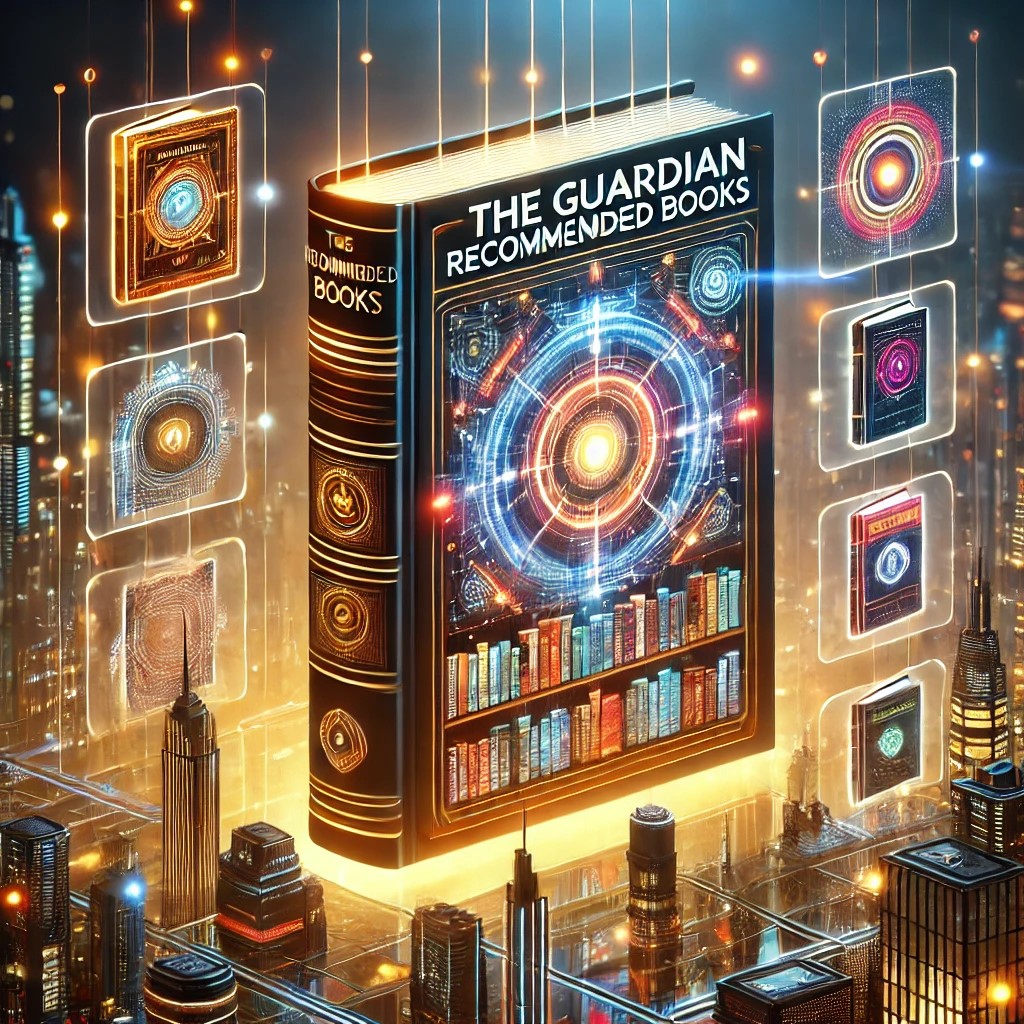
境界知能とグレーゾーンの子供たち(日本評論社/杉山登志郎)
発達障害と境界知能(講談社現代新書/田中康雄)
境界知能の子どもたちへの学習支援(学研/福島玲子)
WISC-Ⅳで読み解く境界知能児の理解と支援(金子書房/井手浩)
自己肯定感を高める子育て(WAVE出版/島村華子)
「自己肯定感低めな人」のための本(大和書房/水島広子)
発達障害の子のためのソーシャルスキルトレーニング(講談社/宮尾益知)
子どもの「生きる力」を育てる本(日本評論社/田中茂樹)
LD(学習障害)の子どもたちへの学習支援(図書文化社/石隈利紀)
発達障害の子の「学ぶ力」を伸ばす本(講談社/佐藤暁)
読み力は生きる力(KADOKAWA/斎藤孝)
ことばが遅れた子のための言語トレーニング(学苑社/宮崎哲男)
「学習性無力感」から抜け出すための授業と支援(明治図書/野口哲典)
発達障害の子どもたちが「できる!」と感じる学び方(小学館/田中康雄)
「勉強しなさい」と言わずに成績が上がる本(PHP研究所/親野智可等)
ケーキの切れない非行少年たち(新潮社/宮口幸治)
弱者の居場所がない社会(山田昌弘)
嫌われる勇気(岸見一郎&古賀史健)
マインドセット(キャロル・S・ドゥエック)
心的外傷と回復(ジュディス・L・ハーマン)
子どもの発達と愛着(ダンヒューズ)
不登校の真実(大森不二夫)
学習障害の子どもへの支援(リチャード・ラヴォイ)
子どもの人格発達の障害(中山書店/斎藤万比古&笠原麻里)
東大よりも世界に近い学校(TAC出版/日野田直彦)
令和型不登校(ぎょうせい出版/神村栄一)
「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を目指して(北大路書房/奈須正裕&伏木久始)

