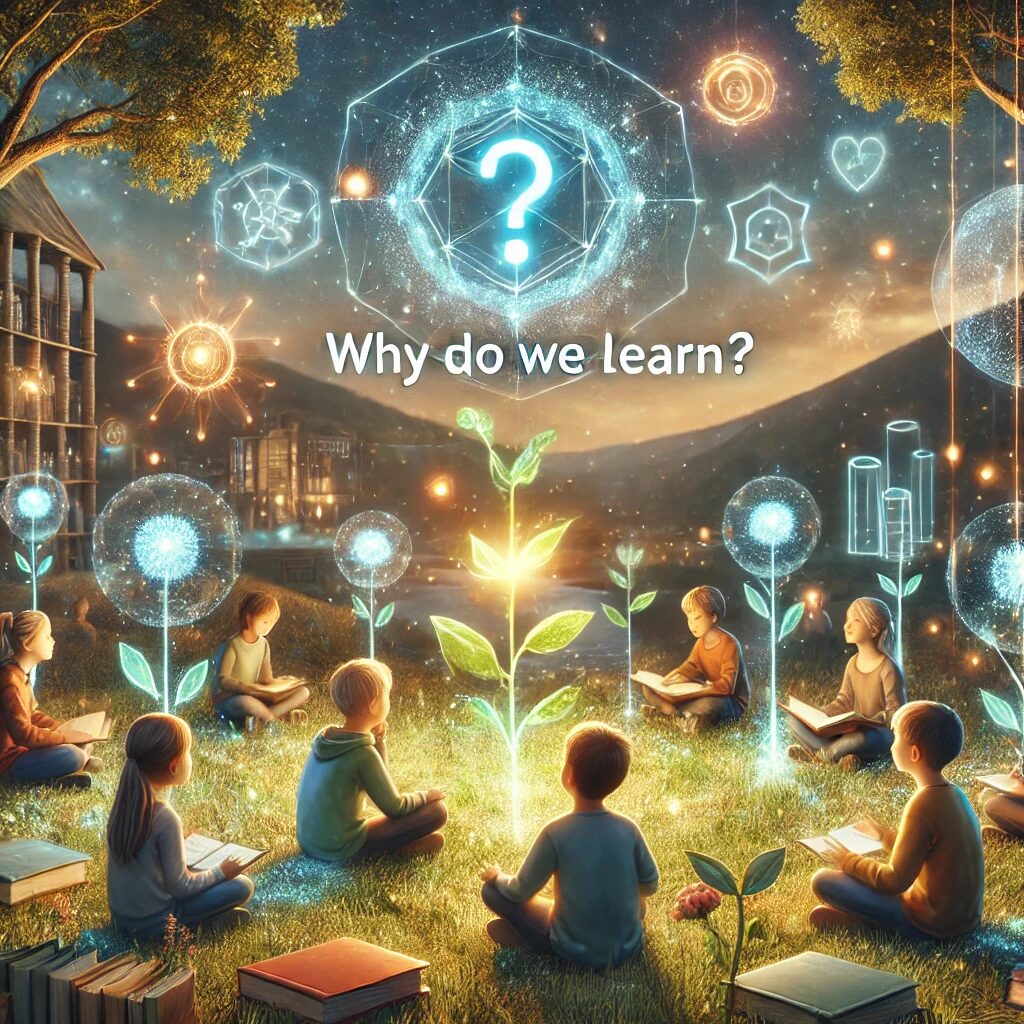
子どもが「学び」を拒む背景
子どもたちが「なぜ学ぶ?」と疑問を抱く時、背景には以下のような状態がある事が多いです。
●学びが「他人事」になっている(自分ごとに感じられない)。
●成功体験が少ない(できた喜びがない)。
●現実との接点が見えない(学んでも意味がないと思っている)。
●過去の失敗やトラウマで「学習=過度な苦痛(意味を感じられず楽しくない)」になっている。
有効なアプローチ
✅1.「生きる」に直結させる学び
今学んでいる事が、将来どんなふうに役立つのかを、子ども自身の人生と結びつける事が大切。
例:
●「計算できると、買い物やバイトで得(好付加価値)をする」。
●読解力があると、クラスメートや仲間との関係もさらによくなる。
●英語が話せると、外国ルーツの家族やお友だちともより仲良くなれる。
●知識があれば、そのぶん自分らしく生きられる。
学びの目的が、自分の幸せや希望とリンクし、更に「将来の経済力」にも繋がる事が肝心。
✅2.興味や関心から逆算する
興味のある事を入口にして学びを設計します。
例:
●ゲームが好き → プログラミングや英語を通して攻略法を学ぶ。
●お絵かきが好き → デザイン・アートの歴史から国語・美術へ。
●動物が好き → 生物・地理・環境問題へと繋ぐ。
興味のある事を通じて、「学ぶのって面白い」と実感させる。
✅ 3. 小さな成功体験を積む
まずは「できた!」を感じる。それが、「学びは自分を助けてくれる」という実感に変わる。
方法:
●ハードルを低く設定 → 成功の確率を高める
●できたらしっかり褒める → ドーパミンで快感記憶に
●成功の「意味」を伝える → 自己効力感につながる
「学ぶこと=できるようになる=嬉しい」というサイクルを作る。
✅ 4. 役割や“誰かの為”で学ぶ意味を見出す
「自分のため」よりも、「誰かの役に立つ」方が、やる気が出る子は多くいます。
例:
●弟に教えてあげられるようになろう。
●学校のプリントを仲間に説明してあげよう。
●「困ってる人を助けたい」から、福祉・心理・法律の学びへ。
? “誰かの役に立つこと”がモチベーションになる子もいる。
✅ 5. メンターやロールモデルとの出会い
「この人のようになりたい」「この人、かっこいい」そう思える大人や年上の存在がいると、学ぶ意義が一気に現実味を帯びます。
具体策:
●進路先の卒業生との座談会。
●現場の仕事に就く人たちと出会わせる。
●学校や地域社会の中でロールモデルを育む。
✅ 6. 「問い」を与える/一緒に問いを立てる
「なぜ?」を大人から投げるだけでなく、子どもと一緒に問いを立てていく姿勢が信頼と学びを生みます。
例:
●「人はなんで生きるんだろう?」
●「どうすれば人は幸せに働ける?」
●「この世界を少しだけ良くするには?」
哲学的・社会的な問いを通じて、学びの意味を見出す。
データの裏付け(参考)
●ハーバード大学 教育学研究所(2018)
「学びの意味づけが明確な子どもは、学力・幸福度・持続的モチベーションが30%以上高い」
●日本教育心理学会(2021)
「成功体験と学習意欲の相関係数はr=0.62(中~強)。学習動機づけに最も影響するのは “自己効力感”」
「なぜ学ぶのか?」を問う子に、答えを与えるのではなく、共に問い、共に探し、共に喜ぶことが、「学び育む」という事ともいえます。
学びの意味は、与えるものではなく「出会う」もの。
その「出会いの場」こそが、Guardianの存在意義なのかもしれません。

