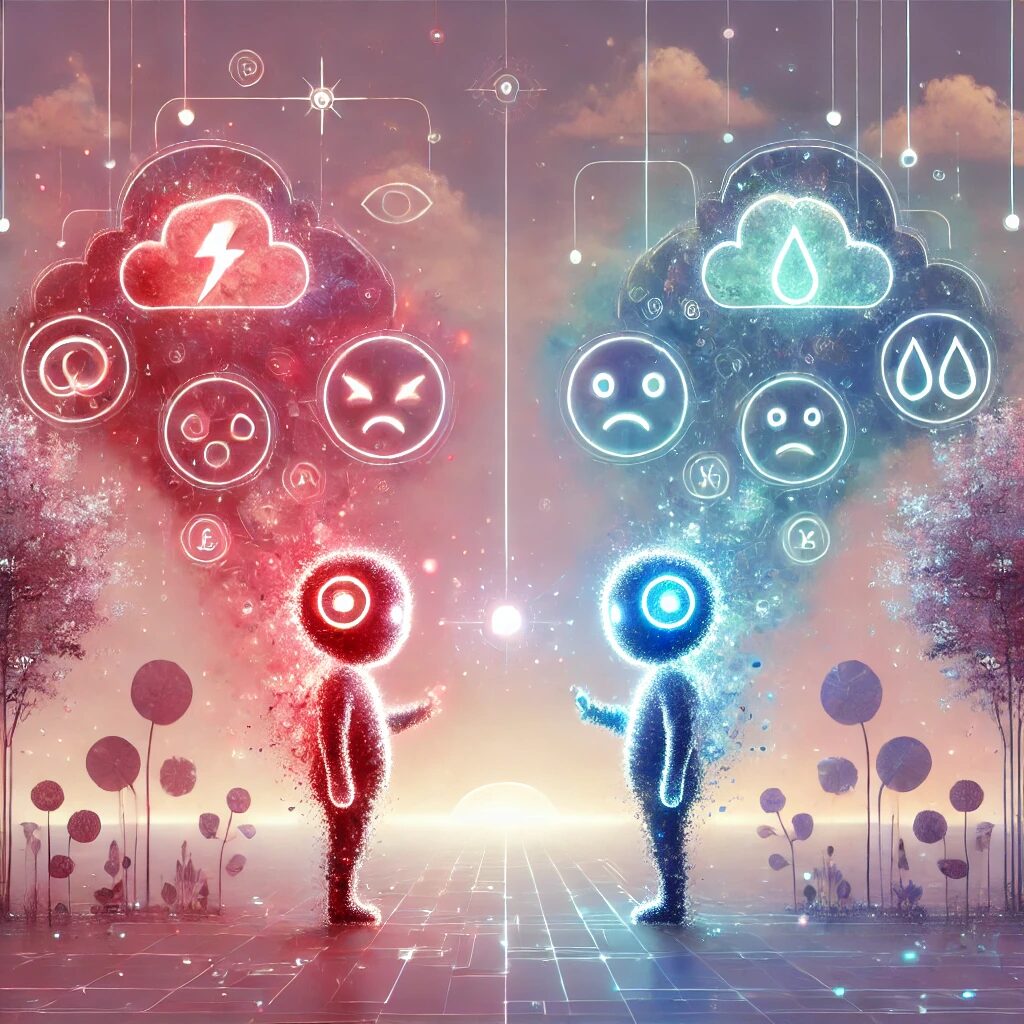
会話から生まれる感情のぶつかり合いを楽しめない世代?
この意味は
「感情のぶつかり合いを楽しめない」とは、単に喧嘩や争いが苦手という事ではなく、
●相手との違いを言語化して受け止める力。
●自分の感情を言葉で表現し、衝突を通じて理解を深める力。
●感情の揺らぎや衝突を、関係性の深化として前向きに捉える感覚。
・・・が、希薄になっている事を指します。
背景にある現代社会の構造
①SNS・デジタル文化の影響
●スタンプ・いいね文化により、曖昧な同調や無言の承認が主流になり、感情の深いやり取りが減少。
●衝突=トラブルと捉え、「波風を立てないコミュニケーション」が評価されやすい。
②家庭・学校での「トラブル(事前)回避型教育」
●「喧嘩しちゃだめ」「感情を出し過ぎないで」と教えられ、感情の衝突を経験する機会が少ない。
●一方で、「空気を読め」「他人に迷惑をかけないように」が強調され、内面を抑圧しがち。
③心の安全基地の希薄さ
●愛着形成が不安定な子どもほど、自分と違う意見や感情に対して強い不安や拒絶感を感じる。
●衝突=見捨てられる、という極端な不安反応に繋がってしまう場合も。
集団指導が発達や成長のチャンスを逃している?
本来、感情のぶつかり合いは「学びと成長の機会」です。
●「あの子はなぜ怒ったのか?」。
●「自分はなぜ悲しくなったのか?」。
●「違う価値観があるって面白いな」。
これらは内省や他者理解のきっかけになります。
しかし現代では、その前段階である「ぶつかる体験」自体が過剰な事前介入で避けられており、
●自己主張が苦手。
●対人ストレスに弱い。
●集団内で自分の居場所がわからない。
●一斉に行う活動では目が行き届かずも埋もれてしまう。
といった問題に繋がっている事があります。
可能なアプローチ
たとえば:
●安全な場で「感情を出しても大丈夫」と伝える体験。
●ぶつかっても壊れない人間関係の模擬体験。
●対話型ワークショップで「違いを楽しむ」スキルの育成。
●ロールプレイやシミュレーションで他者の感情を演じて理解したり、実際の場面を想定して試す。
などを取り入れる事で、「感情のぶつかり合い=危険ではなく豊かさ」として再定義できるものです。
Tweet
