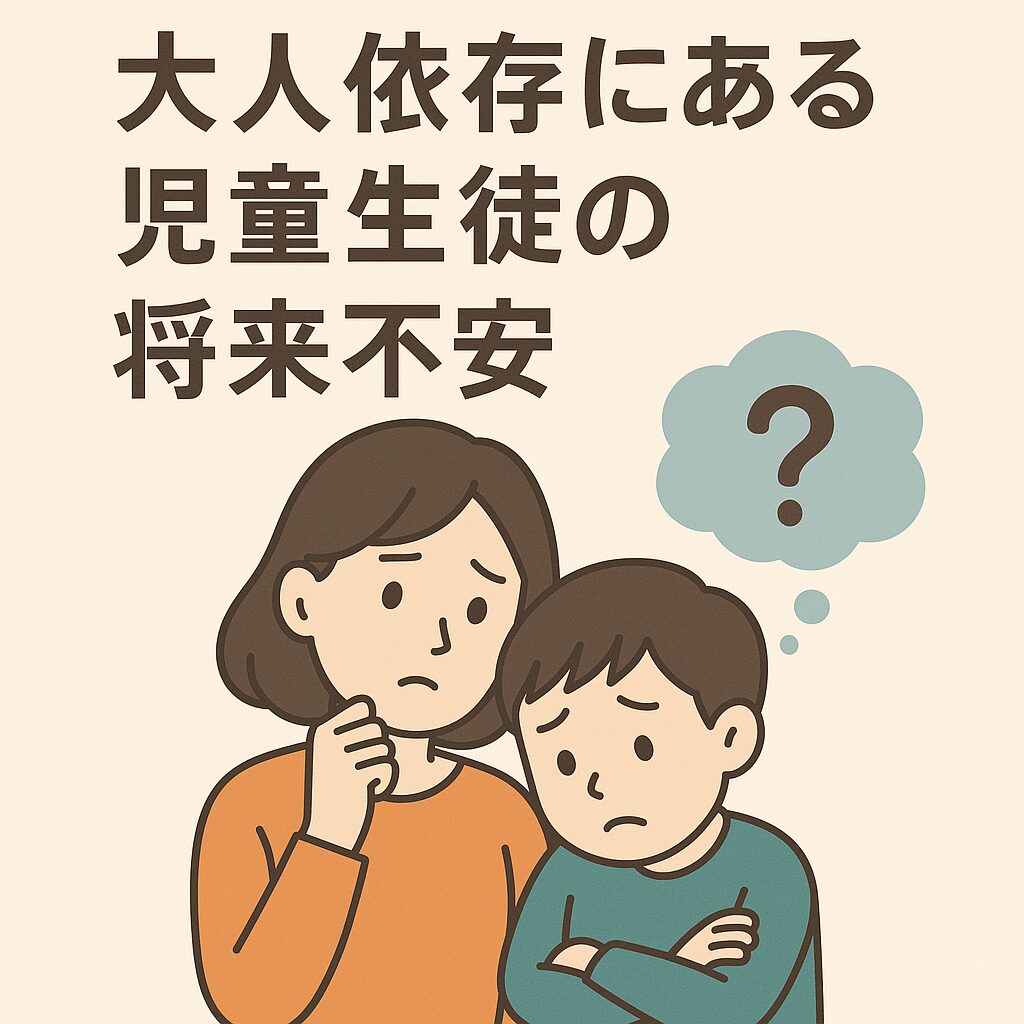
1.愛着障害/依存傾向とは
●愛着障害
●幼少期に安定した愛着関係(主に母子関係)が築けなかった事で、他者との関係性に不適応感が見られる状態。
●特に回避型や不安型の愛着スタイルは、大人に「過剰に頼る/過度なスキンシップ」「見捨てられる不安に敏感」などの行動に表れやすい。
●依存傾向
●発達年齢に対して自立的な行動や自己判断が苦手で、安心できる存在や無条件で大人に過剰に頼る傾向。
●安心基地となる大人が「常にいる」事で、「自己効力感やレジリエンス(心理的回復力)」の獲得機会が奪われやすい。
2.リスクと将来への影響
✅愛着スタイルの弊害が成人期に与える影響
●愛着不安が強い子は、自己調整能力や対人関係のスキルが未発達のまま成人を迎えやすい。
●回避型の子は、一見「自立的」に見えても、本質的な信頼形成が困難で行き詰まりやすい傾向にある。
✅学校・支援環境が「依存を悪化」させてしまう場合のリスク
●学校や放デイでの「遊び・集団行動」の環境において、周囲と関わり難い子が職員に依存しやすい弊害となっている場合。
●職員が「その依存を肯定的(共依存)に扱い続けてしまう」と、年齢相応の“自立機会”や“対等な人間関係”の経験が欠如する場合。
3.現場にありがちな問題と落とし穴
●①集団での遊び体験=万能な協調性学習ではない
●「自由遊び・集団活動・協働」などの活動で、友達と率先して交わる事ができない子が、結果的に大人に依存する事に繋がる狭小選択。
●支援者が、「それでOK(懐かれるのは嬉しい…など)」としてしまう事で、他児者集団との壁が高くなる(環境的社会性の欠如)。
●②成長段階・発達年齢の見誤り
大人が、「可愛いから」「懐いてくれるから」と、「その子らしさ」と「年齢相応の成長」を混同してしまい、発達課題のスルーが起こる。
4.男女で異なるカルチャーショック
| 観点 | 男児 | 女児 |
|---|---|---|
| 依存の対象 | 大人・支援者に対する依存 | 支援者に加えて、疑似恋愛的な依存関係も |
| 社会進出時の衝撃 | 「指示がないと動けない」ため、職場での指示待ち・他責傾向 | 「承認されない事が怖い」ため、過剰な同調・忖度・過労・対人疲弊 |
| 二次障害のリスク | ゲーム依存・引きこもり・就労失敗など | 摂食障害・恋愛依存・性的搾取など |
5.社会人移行期のカルチャーショック
「大人が構ってくれない」「誰も守ってくれない」「どうして良いか自分ではわからない」
この段階で、強い自己否定や無気力に陥るケースは少なくありません。
●主な困難
●指示や支援のない環境への適応障害
●自己決定・自己選択の未経験による学習性無力感や社会的損害
●対人トラブル(過剰な期待 or 疎外感)
6.因果と結果の傾向
◆二次障害・逸脱行動のリスク
愛着障害や依存傾向のある児童生徒は、以下のような「逸脱的な行動」や「心理的孤立」に至りやすい。
①引きこもり(若年無業者)。
②オーバードーズや自傷。
③性的搾取・DV関係への巻き込まれ。
④精神疾患(うつ・不安障害・PTSD)への移行。
7.必要な支援の方向性
✅自立支援へのシフト
●「可愛いから関わる」から、「人権を尊重した自立に導く関わり」へ。
●依存を、「“安心基地”→“自立拠点”」に育てる視点が重要。
✅HEARTモデルの応用
●Relational=「大人との安全な関係」から、Transformational=「自己物語を語れる者」へ。
✅“小さな社会”での擬似体験
●学校や放デイ、習い事などで「ミニ職場体験」「ロールプレイ」「困りごとを一緒に解決する活動」などを設ける。
まとめ
| 視点 | 内容 |
|---|---|
| 課題 | 過剰な大人依存(スキンシップ/パーソナルスペース)と社会性の欠如 |
| 背景 | 愛着スタイルや支援者(大人)側の責任的姿勢 |
| 社会的影響 | 就労困難・人間関係トラブル・社会的逸脱行為 |
| 支援の鍵 | 年齢相応の自立支援/小さな成功体験の積み重ね |
| 大人や支援者の役割 | 「見守る」から「導く」あり方へ |
保護者の方へ
「今、甘えてるように見えるこの子が、18歳になったとき、何を感じるでしょうか?」
お子さんの育ちを日々見守っている中で、「人に甘えすぎているかも…」とか、「なかなかお友達と遊べないな…」と、ちょっと心配になる事はありませんか?男女のパーソナルスペースで言えば、「男女7歳にして席を同じう」と云う、発達年齢に即した関係性を標語する言葉もあります。
でも、つい、「まあ今は楽しいが一番。」「この子なりの成長もある。」と思って、そのままにしてしまう事ありますよね。
今日はそんな、「ちょっとした気づき」が、実は卒業後のその子の生きやすさに繋がる大切なヒントである事をお伝えさせていただきます。
例えばこんな子、思い当たりませんか?
●放デイや学校でお友達とはあまり遊ばず、職員さん・先生ばかりにくっついている。
●他の子とトラブルがあると、すぐに何でもかんでも「先生~!」と頼ってくる。
●大人に褒められたり、かまってもらえる事にとても安心している様子。
このような様子の背景には、「愛着」や「依存傾向」という心の働きが関係している場合があります。
「依存すること」は、ダメな事ではありません
実は、小さい頃に人に頼ることは、とても大切な力です。
「安心できる人に甘えられた」経験は、のちの自立や自己肯定感の土台になります。
でも一方で、その依存の状態が長く続いてしまうと、次のステップに進む準備が難しくなってしまう事があるのです。
データで見る:依存傾向が続く子の「その後」
ある研究(Cassidy & Shaver, 2016)では、愛着が不安定な児童生徒がそのまま成長すると、次のような傾向が見られやすい事がわかっています:
| 年齢 | 主な困りごと |
|---|---|
| 小学高学年生 | 大人への強い依存、友達関係の難しさ、自己主張の弱さ |
| 中・高生 | 不登校・登校渋り、SNSやゲームへの依存傾向、素行不良 |
| 高校卒業後 | 職場や社会での孤立感、自己判断不良、社会的逸脱行為、二次障害 |
これは決して「ダメな子になる」ということではありません。
「大人との関係で安心しすぎて、社会との健全な関わり方を学ぶ機会が減ってしまった」という事なんです。
子どもたちは、多くが18歳で社会に出ていきます。
今の放デイや学校は、職員や先生が優しく丁寧に関わってくれる、保護的環境下にある場です。
でも、社会は「困ったら助けてくれる人がいつもいる」とは限らない現実があります。
だからこそ、「甘えさせながらも、ちょっとずつ自分で出来る事を着実に増やす」関わりが大事になります。
男女で違う「社会への戸惑い」
| 性別 | よく見られる反応 |
|---|---|
| 女子 | 「誰かに認められたい」思いから、過剰に頑張ってしまう/恋愛依存・承認欲求の罠に |
| 男子 | 「誰にも頼れない」と感じて閉じこもる/ゲームやネットに安心を求めて引きこもる |
大人(社会的環境者)との安心な関係性を、「社会での人間関係」として繋げていく練習が、今とても重要とされています。
大切におもうこと
ただ「自立を目指す」ことだけではありません。
「甘えられる安心」と、「自分でやってみる勇気」の両立が大切です。
小さなチャレンジ:
「今日は自分から新しいお友達に話しかけてみたね」
小さな選択:
「どっちの道を進むか、自分で決めてみようか」
・・・こうした日々の細部にこそ、「未来の社会で生き抜く力」が芽生えていきます。
今の愛らしさが、未来の生き辛さにならないように
今、誰かにくっついて安心しているその子が、10年後に「どうしたら良いか分からない…」と立ちすくまないような愛情支援を。
Tweet
