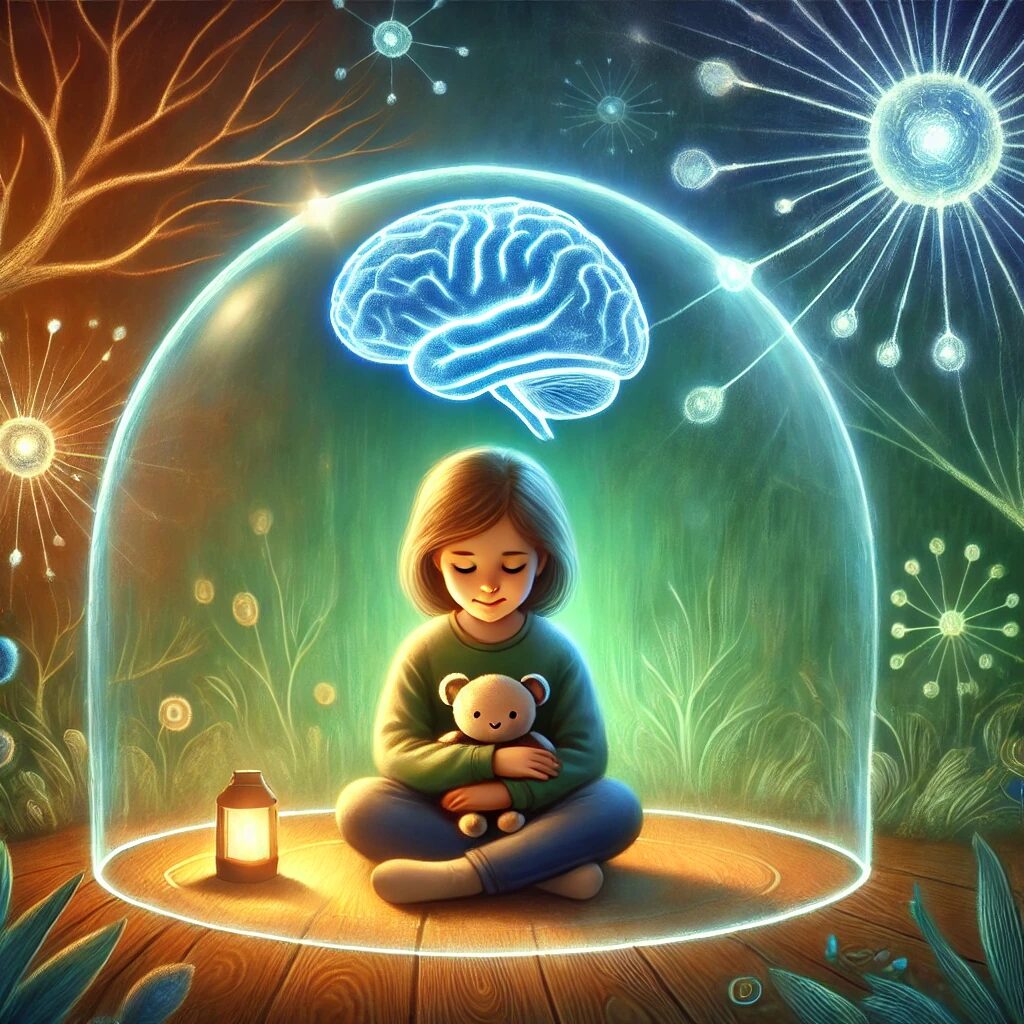
✅「居場所」とは、脳科学的に何を意味するのか
◆居場所とは:定義
「ありのままの自分でいても、安心できる空間」「誰かと “繋がっている” という、感覚を得られる場所」
◆脳科学的視点からの解説
1. 安心できる環境 → 扁桃体の過剰反応が抑えられる
●扁桃体:不安・恐怖・警戒を司る部位。
●居場所がある事で、ストレスホルモン(コルチゾール)が低下。
●脳が、「戦う・逃げるモード」から、「考える・感じるモード」へ。
➡ 脳のエネルギーを「防衛機制」ではなく、「成長発達」に使えるようになる。
2. 安定した人間関係 → オキシトシン分泌が促進
●オキシトシン:信頼・絆・安心感を生む「絆ホルモン」。
●安定した関係性やスキンシップで分泌。
●このホルモンが出ることで、不安や攻撃性が減り、共感性が育つ。
➡ 子どもたちの「社会性」や「愛着の再構築」に効果。
3. 安全な場所 → 前頭前野の発達に繋がる
●前頭前野:計画性、思考、自己制御、道徳判断を司る領域。
●強いストレス下では、この部位の働きが低下。
●安心できる場所があると、前頭前野が正常に働き、自己統制力が回復する。
脳科学での「居場所」の役割まとめ:
| 脳の部位 | 居場所がもたらす影響 |
|---|---|
| 扁桃体 | 不安・警戒の軽減 |
| 視床下部 | ストレスホルモンの抑制 |
| 前頭前野 | 自己制御・共感力の回復 |
| オキシトシン系 | 安心感と信頼関係の育成 |
✅Guardian的「居場所」とは
●生きる意味が問える場所(哲学的)
●失敗しても責められない場所(心理的)
●安心して脳が発達できる場所(科学的)
まとめ
| テーマ | キーワード | 支援視点 |
|---|---|---|
| 境界知能と非行 | 衝動性・孤立・承認欲求 | 居場所と関係性の再構築がカギ |
| 居場所の脳科学 | 扁桃体の抑制、前頭前野の活性 | 安心できる関係性と空間の提供がカギ |
「居場所がある」だけで人は変われる。
「見放された」と感じている子ほど、「見守る存在」があれば大きく進化するものです。

