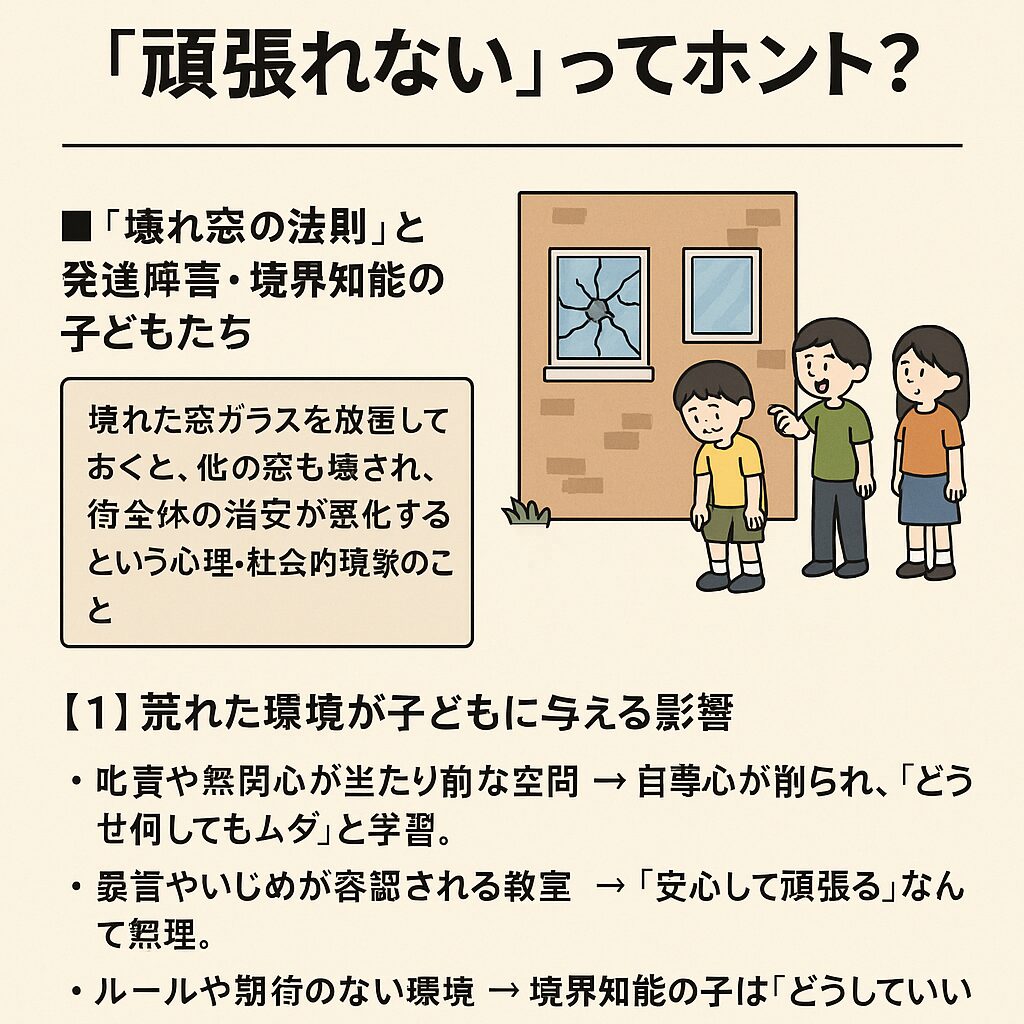
■本当は?:頑張れないのではなく、「別のかたち」で頑張ってる
【1】そもそも「頑張る」とは?
●多くの人が思う「頑張る」は、集中して我慢して、長時間努力し続けるというような、定型的な行動様式を指している事が多いものです。
●しかし、発達障害や境界知能の子は、その「頑張り方」が合わない・うまく出来ない事があるだけで、「本人なりの頑張り」は確実に存在しています。
■【背景にあるもの】
1. 脳の特性
ADHDやASD、LDなどの子どもは、実行機能(記憶・注意の切り替え・自己制御など)に困難がある事が多く、「やらなきゃいけない」とわかっていても「身体や思考が動かない」事が本当にあります。
2. 過去の失敗体験
境界知能や発達障害の子どもは、小さいころから「できないこと」を繰り返し経験し、「どうせやってもムダ」「自分はダメ」と学習性無力感を抱いていることが多いです。
3. 周囲との比較・評価
同じ年齢の子と比べられ、「頑張りが足りない」「怠けてる」と言われ続けると、「頑張ること=また傷つくこと」と捉えるようになり、意欲が削がれてしまうこともあります。
■【支援者が理解すべき視点】
◎「頑張っていない」のではなく、「頑張れない時もある」という理解
●「やる気の問題」ではなく、「脳や心のエネルギーの問題」として捉えることが大切です。
◎「頑張れる形」を一緒に探す
●集中が続かないなら、こまめに休憩を入れる
●記憶が苦手なら、視覚化・音声化する
●動き出せないなら、誰かと一緒に始める
これは、まさに「工夫すれば、頑張れる」という証です。
■【アプローチ】
「HEARTモデル」や「HOPEモデル」では、
●その子に合った頑張り方を設計(A:Adaptive)し、頑張った事を可視化し(T1:成長記録)、物語化(T2:言語化)する事で、子ども自身が「自分でも出来るかも」と思えるように支援していく。
■まとめ:
「頑張れない」のではなく、頑張る方法や形が違うだけ。
その「違い」を理解し、支えてくれる人がいれば、発達障害や境界知能の子どもたちも、確実に力を発揮します。
また、児童生徒の「頑張れるかどうか」には、本人の特性だけでなく、周囲環境の「空気」や「文化」、つまり「場の力」が非常に大きく影響します。
■「壊れ窓の法則」と発達障害・境界知能の子どもたち
「壊れ窓の法則」とは、壊れた窓ガラスを放置しておくと、他の窓も壊され、街全体の治安が悪化するという心理・社会的現象のことです。
これを教育や支援の現場に置き換えると──
【1】荒れた環境が与える影響
●叱責や無関心が当たり前な空間 → 自尊心が削られ、「どうせ何してもムダ」と学習。
●暴言やいじめが容認される教室 → 「安心して頑張る」なんて無理。
●ルールや期待のない環境 → 境界知能の子は「どうしていいかわからない」状態に。
■頑張れる子は、頑張れる空間にいる
発達障害や境界知能の子にとって、「環境」は学習や行動の“インストラクター”そのものです。
例)
●整った空間 → 落ち着きやすい
●肯定的な声かけが多い → 挑戦しやすい
●「頑張った過程」を評価してくれる → 継続しやすい
これらは、まるで「心の窓をきれいに保つ」ような環境整備です。
■環境が心を導く
Guardianでは、「環境」=もう1人の支援者と捉えています。
●空間がポジティブに整備してある
●小さな成功体験を記録する掲示がある
●誰かが失敗しても、みんなでフォローする文化
こうした「仕掛けられた空間」が、「あ、ここでは頑張っていいんだ」と、子どもに感じさせてくれます。
■まとめ:
発達障害や境界知能の子どもが「頑張れるかどうか」は、その子がどんな「場所」にいて、どんな「空気感」の中にいるかに、大きく左右されます。
頑張れない子を責めるよりも、頑張れる環境を整えること。
それが、支援者・教育者・保護者にできる最も効果的なアプローチの一つです。
Tweet
