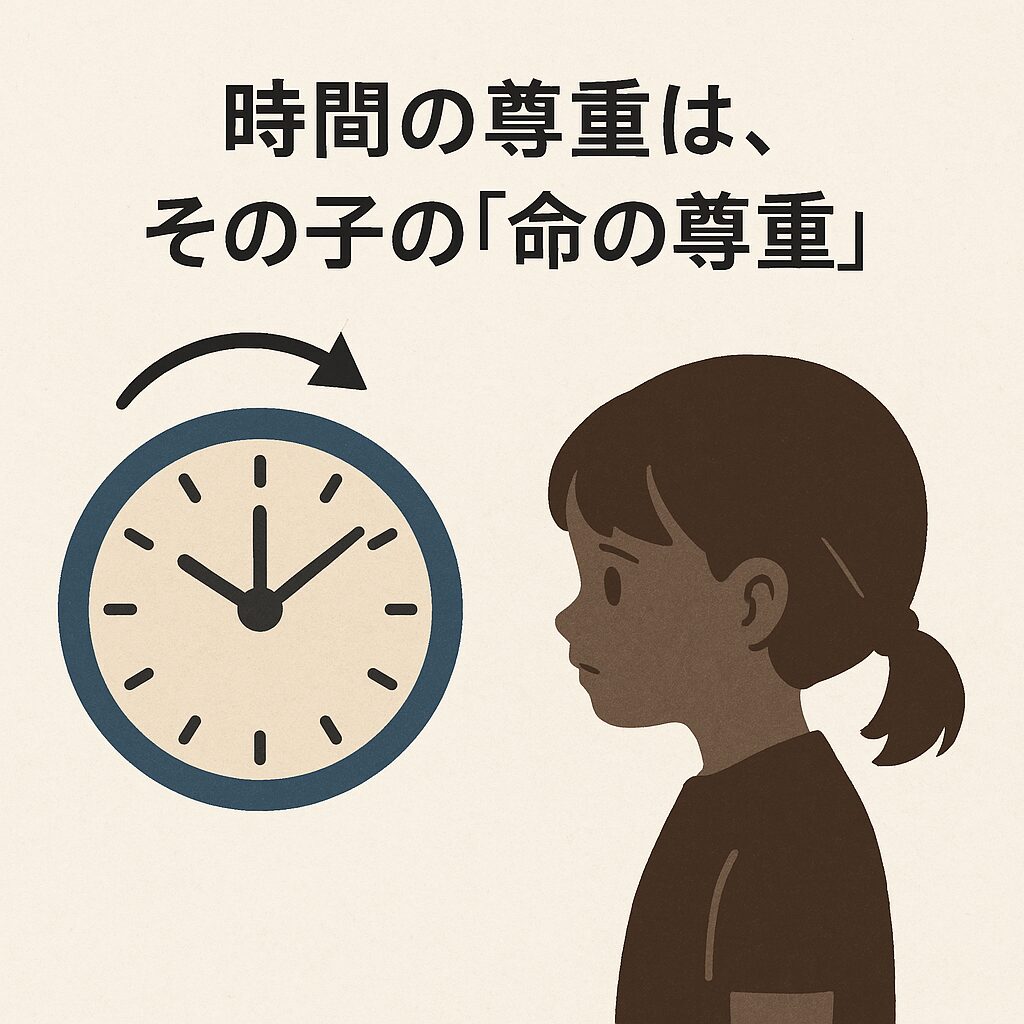
時間の尊重は、その子の「命の尊重」
〜見えない「命の時間」を慈しむ支援へ〜
1.なぜ「時間」が「命」と繋がるのか
人は生きている限り、時間という川の中を流れています。
そして、全ての命に共通している事があります。
それは、「時間には限りがある」という事。
子どもたちが過ごす「今日」という1日は、二度と戻らない、その子の「かけがえのない命の時間」です。
とりわけ、発達障害や境界知能の子どもたちにとっては、その1日1日が成長のチャンスであり、未来へのきっかけでもあります。
2.時間を奪う支援、育む支援
「時間を尊重する」とは、単に「長く関わる」事ではありません。
それは、どれだけ真摯に、その子の「今」に寄り添えるかにかかります。
❌時間を奪う支援とは
●待機だけの時間(指示がないと何もできない)。
●「ねらい」の無い作業の繰り返し。
●特性を理解せず、ただ「やらせるだけ」。
これらは、命の時間を「消費」するだけの関わりです。
✅時間を育む支援とは
●子ども自身が有意味性を感じられる活動。
●「できた!」「わかった!」の達成感ある瞬間。
●感情が動き「生きてる」と実感できる体験。
●自分のペースで過ごせる安心の時間設計。
これらは、命の時間を「育む」支援であり、命の時間を「咲かせる」事にも繋がります。
3.Guardianが大切にする「時間設計」
私たちGuardianが考える支援の本質は、「子どもの今日を、未来に繋がる意味のある時間にする事」です。
たとえば、HEARTメソッドにおける時間設計は、以下のような問いを軸にします。
●この時間が、その子にとって「人として大切にされた実感」になっているか?
●感情が動き、誰かと「心が通った時間」になっているか?
●自分の事を知り、「これが自分なんだ」と感じられたか?
4.「命の時間」を慈しむということ
子どもたちの「命の時間」を、何で埋めていくかは、支援者の「覚悟」にかかっている。
・その子の好奇心。
・希望の芽。
・感情の揺れ。
・自分で選ぶ権利。
・生きる意味を感じられる経験。
それら全てを乗せた「時間」を、私たち大人は一緒に紡いでいるのです。
だからこそ、1分1秒を「ただの作業」にせず、「命ある物語り」にしていく事。
それが、時間の支援であり、「命の支援」なのだと思います。
まとめ
「時間の尊重」とは、その子の命を大切にする事。
支援とは命の時間に「意味」を与える行為。
だから1日の設計は、「未来を描く祈り」そのもの。
~「退屈」と「しんどさ」に込められた、心のSOSを聴く~
1.「退屈」は、ただの「暇」ではない
「退屈」という言葉は、ただの時間の「空白」を意味しません。
それは、「自分の存在が満たされていない」という、内なるサインでもあるのです。
子どもの声:「なんか退屈」
心の声:
●「やる事がない」= 何をしていいか、自分で選べない・選ばせてもらえない。
●「楽しくない」= 自分にとって意味がない活動。
●「つまらない」= 自己表現ができない、感情が動いていない。
心理学的エビデンス
●発達心理学では、「退屈は行動の自己決定性が奪われた時に発生する」とされています(Eastwood et al., 2012)。
●また、「自己決定理論(Deci & Ryan)」においては、「選択の自由」「有能感」「関係性」が奪われると、内発的動機づけが低下し、無気力や退屈感に繋がると報告されています。
つまり、「退屈だ・・・」という状態は、心理的ニーズの未充足=SOSでもあるのです。
2.「頭が痛い…」は、環境への「適応困難」のサイン
特に、発達特性をもつ子どもたちは、感覚過敏やストレス反応から「身体症状として訴える」事が多くあります。
子どもの声:「頭が痛い」「お腹が痛い」
心の声:
●「音がうるさい」「人が多くて落ち着かない」。
●「空気感がピリピリしていて、心が苦しい」。
●「指示や活動が早すぎて、ついていけない」。
科学的エビデンス
●感覚統合に関する研究(Ayres, 1979)は、環境刺激が過度だと、ストレス反応が身体化しやすい事を指摘しています。
●児童精神科の臨床では、「身体症状(頭痛・腹痛)」は、「心因性ストレスの“訴えの形”」として頻出します。
●自閉スペクトラム症では、身体での「表現」が優位になるケースも多い(DSM-5・日本自閉症協会報告)。
3.「退屈」と「身体症状」は命の時間からのメッセージ
このように、子どもたちの「退屈だ」「しんどい」という声は、命の時間が「今、無下に消費されている」という警報です。
私たちには、その声を「命の声」として聴き取るアンテナ感度が求められます。
4.時間設計:命の声を聴くプログラム
✅心のSOSを未然に防ぐ3つの軸
●選択肢を持たせる(=自己決定を尊重)。
●意味を感じられる活動にする(=本人にとっての納得)。
●安心できる空間をつくる(=感覚・関係・心理的安全)。
5.支援者が意識すべき問い
●今日の活動は、「その子の命の時間」にとって価値があったか?
●「退屈」「しんどい」と言わせる前に、「兆し」を感じ取れていたか?
●時間の設計が、「その子の存在の肯定」になっているか?
まとめ:時間とは命のカケラである
「退屈」と「しんどい」は、命の時間からの「問いかけ」。
それを聴く事は、その子の「存在」と「命のリズム」を慈しむ事。

