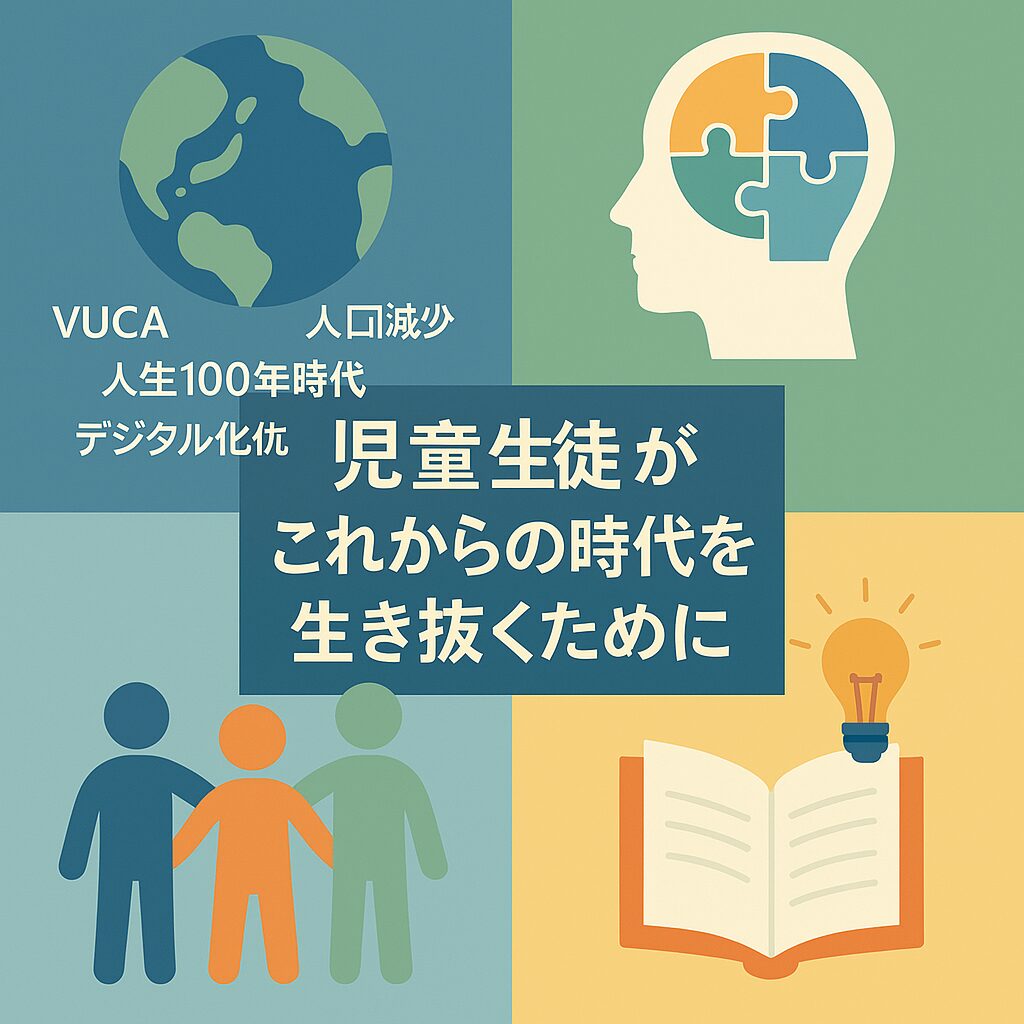
VUCA、人口減少、人生100年、デジタル社会など、いくつもの社会的なキーワードがありますが、これから先の時代を生きていく上で、児童生徒が身につけるべき資質や能力、また教育現場ではどのような視点が求められてくるだろう?
背景キーワード
1.VUCA時代:変動(Volatility)、不確実(Uncertainty)、複雑(Complexity)、曖昧(Ambiguity)。
2.人口減少・少子高齢化社会:一人ひとりの役割が増し、共助・多様性が重要に。
3.人生100年時代:学びと働きが一生続く時代へ。
4.デジタル・AI時代:情報リテラシー・創造性・人間性のバランスが鍵。
5.持続可能性(SDGs)・共生社会:「私たち」という視点が問われる社会。
児童生徒が身につけるべき資質・能力
1.VUCAに備える力
●レジリエンス(心のしなやかさ)。
●意思決定力と自己理解。
●変化をおそれない柔軟性。
2.人口減少社会に必要な力
●共助・共生のコミュニケーション能力。
●複数役割を担うマルチスキル。
●自分の存在意義を感じる力(アイデンティティ)。
3.100年時代を生き抜く力
●学び続ける力(ラーニングスキル)。
●身体・精神のセルフマネジメント。
●意味づけ力(自分なりの「幸せ」を定義する力)。
4.デジタル時代を生き抜く力
●情報リテラシー/メディアリテラシー。
●創造性・表現力(特に非言語含む)。
●人と繋がる「温かさ」や「感情の認識力」。
教育現場で求められる視点
1.個別最適化と多様な学びの保障
●発達特性・学習スタイルに応じたユニバーサルデザイン教育。
●発達障害・境界知能の児童生徒にも「選択肢」を与える。
●学校外リソース(放課後等デイ・ICT・地域)との連携。
2.「感情と関係性」を育む支援
●SEL(社会性と情動の学習)や感情の可視化ツールの導入。
●安心できる関係性の中で「やってみたい」が育つ環境整備。
●支援者の共感力と関係構築スキルの向上。
3.「生きる意味」を育む支援
●キャリア教育を「自分の物語を描く教育」へと再定義。
●成長記録やナラティブ(物語)ベースの振り返り支援。
●「誰かの役に立てた経験」を通じた自己効力感の強化。
4.デジタルとアナログの「共創」
●情報活用・表現スキルを学習に横断的に組み込む。
●「創作・発信する喜び」を体感するプロジェクト型学習。
●メタバース・VRなども含む「共感型デジタル体験」の活用。
アプローチの提案
例えば、HEARTメソッドに当てはめると──
●H(Human):その子の「得意・好き」をベースに育む。
●E(Emotional):感情を言葉(具現化)にできるよう支援する。
●A(Adaptive):不確実な未来に向け「希望」と「現実適応」を繋ぐ。
●R(Relational):「誰かと関わる喜び」を体感する機会づくり。
●T(Transformational):自分の物語に意味を見い出せるような記録支援。
未来を拓くキーワードまとめ
| 時代背景 | 子どもたちに必要な力 | 教育・支援の方向性 |
|---|---|---|
| VUCA時代 | レジリエンス、柔軟性 | 自己理解・判断力の育成 |
| 人口減少 | 共生スキル、多様性の尊重 | コミュニティ連携・役割体験 |
| 人生100年 | 学び続ける力、意味づけ力 | キャリアとウェルビーイングの統合 |
| デジタル時代 | 情報活用力、創造性、共感力 | デジタル×人間性の教育設計 |
グローバルな視点から見た教育の最新動向
1.OECDの「Education 2030」プロジェクト
OECDは「Education 2030」プロジェクトを通じて、未来の教育とスキルに関するビジョンを提示しています。
このプロジェクトでは、学生が2030年に向けて必要とされる知識、スキル、態度、価値観を特定し、教育システムがそれらを効果的に育成する方法を探求しています。
2.UNESCOの「持続可能な開発の為の教育(ESD)」
UNESCOは、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、教育が果たす役割を強調しています。
特に、教育を通じて持続可能な開発に必要な知識、スキル、価値観を育む事が重要視されています。
児童生徒が身につけるべき資質・能力
1.21世紀型スキル
グローバルな視点から、以下のスキルが重要とされています:
●学習・革新スキル:クリティカルシンキング、問題解決、コミュニケーション、コラボレーション、創造性。
●デジタルリテラシースキル:情報リテラシー、メディアリテラシー、ICTリテラシー。
●キャリア・人生スキル:柔軟性、適応性、自己主導性、社会的・異文化的スキル、生産性、責任感。
2.持続可能な開発の為のコンピテンシー
UNESCOは、持続可能な開発を推進するために以下のコンピテンシーを挙げています:
●システム思考能力:複雑なシステムを理解し、全体的な視点で考える力。
●予測的思考能力:将来のシナリオを想定し、計画を立てる力。
●規範的思考能力:価値観や倫理観に基づいて判断し、行動する力。
●戦略的能力:効果的な戦略を立案し、実行する力。
●コラボレーション能力:多様なステークホルダーと協働する力。
●クリティカルシンキング:情報を批判的に評価し、判断する力。
●自己認識能力:自己の価値観、信念、行動を理解し、反省する力。
●統合的問題解決能力:多角的な視点から問題を解決する力。
教育現場で求められる支援の方向性
1.デジタルスキルの強化
AIやデジタル技術の急速な進化に伴い、教育現場ではデジタルリテラシーの向上が不可欠です。
指導者自身がデジタルスキルを習得し、生徒に適切な指導を行う必要があります。
2.社会的・情動的スキルの育成
OECDの調査によると、日本のティーンエイジャーは他国に比べて社会的・情動的スキルが低いとされています。
教育現場では、これらのスキルを育成するプログラムの導入が求められています。
3.持続可能な開発教育の推進
持続可能な社会を実現する為には、教育を通じて持続可能な開発に関する知識や価値観を伝える事が重要です。
カリキュラムにESD(持続可能な開発の為の教育)を組み込む事で、生徒の意識を高める事ができます。
まとめ
これからの時代を生き抜く為には、児童生徒が21世紀型スキルや持続可能な開発の為のコンピテンシーを身につける事が不可欠です。
教育現場では、デジタルスキルの強化、社会的・情動的スキルの育成、持続可能な開発教育の推進といった支援が求められます。
これらを実現する為には、指導者自身のスキル向上やカリキュラムの見直し、地域社会との連携が重要となります。
更に、教育の場でAIやデジタル技術を活用する際には、倫理的な視点や人間性を重視したアプローチが必要です。
ESD(Education for Sustainable Development)とは
「持続可能な開発のための教育」の事です。
国連(UNESCO)が提唱する教育の理念であり、持続可能な社会を創る為に必要な「価値観・知識・態度・行動」を育てる教育を指します。
簡単に言うと?
未来の「地球・社会・命」のために、今、どう生きるかを学ぶ教育。
ESDの基本的目的
●地球規模の課題(環境、貧困、平和、人権など)を理解する。
●問題解決に向けて、「自分事」として考え、行動する力を育てる。
●持続可能な社会づくりに参加できる人材を育成する。
ESDが取り組む主なテーマ
●環境問題(地球温暖化、プラスチック汚染など)。
●貧困・格差(貧困層の支援、多文化共生など)。
●人権・ジェンダー(差別、包摂、平等の理解など)。
●平和と非暴力(紛争解決、共存の視点など)。
●持続可能な消費・生産(リサイクルやフェアトレードなど)。
●地域社会との関係性(ローカルな文化・環境の保全など)。
ESDが目指す学びのスタイル
| 従来の教育 | ESD的教育 |
|---|---|
| 知識の習得が中心 | 気づき→考える→対話→行動 |
| 答えは一つ | 答えは多様、プロセス重視 |
| 教師が教える | 子どもが主体的に探求 |
| 評価は点数 | 変容・成長・行動の変化も評価対象 |
キーワード
●Think Globally, Act Locally(地球規模で考え、地域で行動)。
●未来志向/共生/参加/対話/多様性/協働。
日本ではどう活用されている?
●「SDGs教育」とも強くリンクしており、文部科学省も「ESDの推進」を教育方針に明記。
●「小・中・高校」の総合的な学習・探究の時間で活用。
●「地域課題」と結びついた探究・体験活動(例:地域資源を活かしたプロジェクト)。

